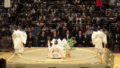夏の夜空を彩る祭り、神社の境内を埋め尽くす縁日。そこには必ずと言っていいほど、たこ焼き、りんご飴、金魚すくいといった出店が並び、我々の心を躍らせる。この出店を営む人々が「テキ屋」である。しかし、その賑やかでノスタルジックな光景の裏には、深く、時に暗い世界が広がっている。
反社会的勢力との繋がり
テキ屋の闇を語る上で避けて通れないのが、反社会的勢力、特にヤクザとの歴史的な関係だ。
縄張りと場所代
伝統的に、テキ屋はヤクザの稼業の一つと見なされることが多かった。祭りが開かれる場所には「縄張り」が存在し、その土地を仕切る組織の許可なく出店することは不可能であった。
出店するテキ屋は、その組織に対して「場所代(ショバ代)」や「みかじめ料」といった名目で上納金を支払う。これは、場所を借りる対価であると同時に、他の介入者から守ってもらうための「保護料」の意味合いも持っていた。このシステムが、ヤクザの大きな資金源の一つとなっていたのである。
親分子分の盃事
テキ屋の組織は、ヤクザと同様に「親分・子分」の強固な縦社会で成り立っている。盃事を交わすことで生まれるこの関係は、単なる雇用関係ではなく、絶対的な忠誠を求める擬似的な家族関係に近い。組織の掟は厳しく、逆らうことは許されない閉鎖的な世界がそこにはある。
閉鎖的な組織構造と搾取
テキ屋の世界は、一見すると独立した個人事業主の集まりに見えるかもしれない。しかし、その内部には厳しい徒弟制度と搾取の構造が存在する。
若い衆は、親方の下で住み込み、食事や寝床を提供される代わりに、無給に近い形で過酷な労働を強いられることが多い。売上の大半は「上がり」として親方に吸い上げられ、手元にはわずかな小遣いしか残らない。このような封建的な関係は、外部からは見えにくい搾取の温床となり得る。
不透明なカネの流れ
テキ屋の商売は、そのほとんどが現金決済である。一日で大きな金額が動くにもかかわらず、その売上の実態が外部から正確に把握されることは極めて難しい。この不透明性は、所得を過少に申告するなどの「脱税」に繋がりやすい構造的な問題をはらんでいる。組織に納められた上納金が、どのように使われ、どこへ流れていくのかもまた、闇の中である。
時代の変化と新たな闇
近年、警察による「暴力団排除条例(暴排条例)」の施行と強化により、この伝統的な構造は大きく揺らいでいる。祭りの主催者(神社や自治体など)が、暴力団関係者と取引を行うことが条例で禁止されたからだ。
これにより、これまでテキ屋を仕切ってきた伝統的な組織は排除され、表向きはクリーンになったように見える。しかし、その変化が新たな闇を生んでいる側面もある。
- 偽装と潜伏: 伝統的な組織が、一般企業を装ったフロントカンパニーを設立し、主催者側と契約を結ぶケースがある。実態は変わらないまま、巧妙に条例の網をくぐり抜けようとする。
- 「半グレ」の台頭: 暴排条例の対象とならない、より緩やかで実態の掴みにくい反社会的グループ「半グレ」が、テキ屋のビジネスに参入する例が増えている。彼らは伝統的な仁義や掟に縛られず、より悪質で短期的な搾取を行う傾向があり、新たなトラブルの原因となっている。
- 素人集団による質の低下: 伝統的なテキ屋が締め出された隙間を、単なる金儲けが目的の素人集団が埋めることもある。これにより、食品衛生の管理がずさんになったり、客とのトラブルが頻発したりと、サービスの質の低下が懸念される。
我々が目にする賑やかな出店の光景は、時にこうした複雑で根深い問題の氷山の一角なのかもしれない。祭りの灯りが照らし出す楽しげな風景の裏で、その構造は静かに、しかし確実に変化し続けているのである。
神社内の場所は誰がどうやって決めているのか
祭りの日に神社の境内や参道を彩る数々の出店。一見、雑然と並んでいるように見えて、そこには一定の秩序が存在する。その場所は、一体誰が、どのようにして決めているのだろうか。
かつての仕組み:テキ屋組織による支配
かつて、祭りの出店場所は、その地域「縄張り」とするテキ屋の組織、特にその長である「親分」や「顔役」と呼ばれる人物が絶対的な権限を握っていた。
場所の割り振りは、新規の者や若い者よりも、長年その祭りで商売を続けてきた「古株」が優先された。人通りの多い一等地は、組織内での地位や親分との関係性が深い者に与えられるのが常であった。テキ屋の隠語で、出店場所の割り振りを「テイタ割り」と呼ぶ。これは親分の采配一つで決まり、その決定は絶対であった。
現在の仕組み:暴力団排除条例後の変化
この伝統的な仕組みの大きな転換点となったのが、「暴力団排除条例(暴排条例)」である。これにより、祭りの主催者(神社や地域の奉賛会、自治会など)は、暴力団関係者を出店させることが固く禁じられた。結果として、場所決めの主導権はテキ屋組織から祭りの主催者へと大きく移行した。
主催者による直接管理
現在、多くの祭りでは、神社や祭りの実行委員会が主体となって出店者を公募し、場所の割り振りまでを直接管理する方式が主流となっている。主催者は出店希望者から申込書を提出させ、その内容を審査して出店の可否を決定する。
警察との連携と指導
主催者は、出店希望者が反社会的勢力と無関係であることを確認する義務を負う。そのため、申込者リストを所轄の警察署に提出し、暴力団関係者でないかどうかの照会を行うのが一般的である。警察の指導の下、透明性と公平性を確保することが求められる。
出店場所の割り当ては、安全性の確保や来場者の動線、業種のバランスなどを考慮して主催者側が決定している。
このように、神社の出店の場所決めは、かつての力と仁義が支配した暗黙の世界から、法律とコンプライアンスに基づき、主催者が公的な責任の下で管理する透明な世界へと、その姿を大きく変えつつある。
道路(歩行者天国)は、警察が決めているの?それとも神社?
祭りの際に現れる歩行者天国。その交通規制は、神社と警察、どちらの判断によるものか。結論から言えば、最終的な許可権者は警察である。しかし、そこには神社(主催者)との密接な連携が存在する。
それぞれの役割
歩行者天国が実現するまでには、神社と警察がそれぞれの役割を担い、手続きを進める必要がある。
神社(主催者)の役割:申請者
まず、祭りを主催する神社や地域の実行委員会が、「祭礼の円滑な運営と、参拝者・来場者の安全確保のために交通規制が必要である」と判断することから全てが始まる。
主催者は、いつ、どの区間を、どのくらいの時間にわたって歩行者天国にしたいかという具体的な計画を立てる。そして、う回路の案内や警備員の配置といった安全対策を盛り込んだ「道路使用許可申請書」を作成し、その道路を管轄する警察署に提出する。つまり、神社は「申請者」としての役割を担うのである。
警察の役割:許可権者
申請を受けた警察は、道路交通法に基づき、その申請内容を厳格に審査する。交通への影響や公共の利益、安全対策の妥当性などを総合的に判断し、問題がないと認められた場合に、所轄の警察署長の名で「道路使用許可」が下りる。
この許可をもって、初めて歩行者天国という交通規制が正式に決定される。警察は、公の安全と秩序を守る「許可権者」なのである。
このように、歩行者天国の実現は、主催者である神社の「願い(申請)」を、交通秩序の管理者である警察が「聞き入れ(許可する)」という、両者の協力関係の上に成り立っている。
過去のニュース
暴力団であることを隠して出店する「詐欺」の事例
警察の捜査により、暴力団員であることを隠して、祭りの出店権利をだまし取ったとして逮捕される事例が複数報告されている。
- 浜松まつり・沼津夏まつり(静岡県)
- 2022年から2023年にかけて、静岡県内で開催された複数の祭りで、指定暴力団の組員らが露店商の名前を借りたり、実質的な経営者であることを隠したりして、露店を出店する権利をだまし取ったとして詐欺容疑で逮捕されている。
- こうした手口で得た売上が、暴力団の資金源になっていたとみられている。ある事例では、暴力団の総長が、出店料の名目で露店から1,200万円以上を得ていたという報道もある。
公募制の裏側で暗躍する「名義貸し」の事例
祭りやイベントの主催者が、暴力団排除条例に則り、出店者を公募する形式に移行するなかで、それをかいくぐるための違法行為も摘発されている。
- 露天商組合の理事長が逮捕された事例
- 浜松まつりの事例では、露天商組合の理事長が、暴力団関係者と知りながら出店の手助けをしたとして逮捕されている。これは、公募制や暴力団排除を掲げる主催者に対して、暴力団員ではない人物を名義人として登録させる「名義貸し」に協力したとみられる。
祭りのパトロール強化と摘発
警察は、テキ屋と暴力団との関係を断ち切るため、祭りの期間中に重点的なパトロールを実施している。
- 静岡県警の初詣パトロール
- 正月などの大規模な祭事では、警察官が露店を巡回し、出店者に対して組合員証などの提示を求め、暴力団とのつながりがないか入念にチェックする取り組みが行われている。
- これは、過去の逮捕事例を教訓に、違法な出店を未然に防ぐための措置だ。
これらの事例からわかるように、暴力団排除条例によってテキ屋を取り巻く環境は大きく変わった。しかし、暴力団側も組織の資金源を維持するために、より巧妙な手口で祭りのビジネスに関わろうとしている。警察や主催者側もそれに負けじと、摘発や監視を強化している状況だ。
一方、反社会的勢力との関わりとは全く違う、テキ屋の良い行いに関するニュースもある。
災害時の炊き出しボランティア
東日本大震災や熊本地震、能登半島地震といった大規模災害の際、多くのテキ屋(露天商)が被災地に駆けつけ、炊き出しボランティアを行ったという事例が多数ある。
- 素早い行動力: 平時から多くの食料や調理器具をトラックに積んでいるため、災害発生後すぐに被災地へ向かい、温かい食事を届けられる。
- 専門技術の提供: 焼きそばやお好み焼きといった屋台料理は、一度に大量の食事を作ることができ、避難所の人々に喜ばれたという。
- 心のケア: 被災者にとって、温かい食事は空腹を満たすだけでなく、非日常の中で「お祭り」のような賑わいを感じさせる心のケアにもつながった。
これは、普段は商売敵でも、災害という非常事態には一致団結して助け合う、テキ屋ならではの絆があるからだと言われている。