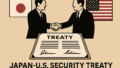1945年8月、広島と長崎に原子爆弾が投下された。しばしば「トルーマン大統領が命令した」と単純に語られる。命令前、トルーマンは原爆の破壊力が尋常ではないことを知っていたが「一発で10万人死ぬ」という正確な数字を把握していたわけではない。被害規模の認識は、実際の投下後に深まった側面が大きい。
また、当時、原子爆弾投下に反対している高官が多くいたことは、あまり知られていない。
また、驚くことに、実際には、トルーマンは2発目の原爆投下に驚きと不快感を示したという記録すら存在する。
この記事では、1945年7月25日付の原爆投下命令書の原文と、軍部とトルーマンの意思決定構造を紐解きながら、「誰が」「どうやって」原爆投下を決定したのか、またその理由を明らかにする。
広島・長崎の被害状況
広島・長崎の被害状況を表にまとめます。
| 項目 | 広島 | 長崎 |
|---|---|---|
| 投下日時 | 1945年8月6日 午前8時15分 | 1945年8月9日 午前11時02分 |
| 爆弾名 | リトルボーイ(Little Boy) | ファットマン(Fat Man) |
| 爆心地 | 広島市中心部(相生橋付近) | 長崎市松山町上空 |
| 爆発高度 | 約600メートル | 約500メートル |
| 死者(推定) | 約14万人(1945年末までの推計) | 約7万人(1945年末までの推計) |
| 負傷者 | 約7~8万人 | 約7万人 |
| 建物の全壊・焼失率 | 約70%(爆心地から2km圏内はほぼ全壊) | 約36%(爆心地から1.5km圏内で壊滅) |
| 被害範囲 | 半径約2kmで壊滅。爆風と熱線は半径約4kmまで | 半径約1.5kmで壊滅。爆風と熱線は半径約3kmまで |
トルーマンの命令は包括的だった
1945年7月25日、アメリカ陸軍参謀本部 参謀総長代行 トーマス・T・ハンディ将軍が署名し、アメリカ陸軍戦略空軍司令官 カール・スパーツ将軍に宛てた「原爆使用に関する命令文書」は、以下のとおりである。
Memo for General Carl Spaatz
WAR DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF OF STAFF
Washington 25, D. C.
25 July 1945TO: General Carl Spaatz
Commanding General
United States Army Strategic Air Forces1. The 509 Composite Group, 20th Air Force will deliver its first special bomb as soon as weather will permit visual bombing after about 3 August 1945 on one of the targets: Hiroshima, Kokura, Niigata and Nagasaki. To carry military and civilian scientific personnel from the War Department to observe and record the effects of the explosion of the bomb, additional aircraft will accompany the airplane carrying the bomb. the observing planes will stay several miles distant from the point of impact of the bomb.
2. Additional bombs will be delivered on the above targets as soon as made ready by the project staff. Further instructions will be issued concerning targets other than those listed above.
3. Dissemination of any and all information concerning the use of the weapon against Japan is reserved to the Secretary of War and the President of the United States. No communiques on the subject or releases of information will be issued by Commanders in the field without specific prior authority. Any news stories will be sent to the War Department for special clearance.
4. The foregoing directive is issued to you by direction and with the approval of the Secretary of War and of the Chief of Staff, USA. It is desired that you personally deliver one copy of this directive to General MacArthur and one copy to Admiral Nimitz for their information.
THOS. T. HANDY
General, G.S.C.
Acting Chief of Staff
スパーツ将軍宛メモ
1945年7月25日
陸軍省
参謀総長室
ワシントンD.C. 25
1945年7月25日
宛先: カール・スパーツ将軍
アメリカ陸軍戦略空軍司令官
- 第20空軍第509混成部隊は、1945年8月3日頃以降、視認による爆撃が天候上可能になり次第、最初の特殊爆弾を広島、小倉、新潟、長崎のいずれかの目標に投下する。陸軍省から軍および民間の科学要員を搭乗させ、爆弾の爆発効果を観察・記録するため、爆弾搭載機に追加の航空機が随行する。観測機は爆弾の着弾地点から数マイル離れて待機する。
- 追加の爆弾は、プロジェクトスタッフの準備ができ次第、上記の目標に投下される。上記以外の目標については、追って指示が出される。
- 本兵器の対日使用に関するあらゆる情報の開示は、陸軍長官およびアメリカ合衆国大統領に留保される。現場の指揮官は、事前の具体的な許可なくして、本件に関するコミュニケ(公式に発表する声明)や情報の発表を行ってはならない。あらゆるニュース記事は、特別な承認を得るため陸軍省に送付されるものとする。
- 上記の指令は、陸軍長官およびアメリカ陸軍参謀総長の指示と承認に基づき、あなたに発令されたものである。本指令の写し1部をマッカーサー将軍に、もう1部をニミッツ提督に、それぞれ情報として個人的に手渡していただきたい。
トーマス・T・ハンディ
https://www.atomicarchive.com/resources/documents/manhattan-project/spaatz-memo.html
陸軍将軍、参謀本部
参謀総長代行
つまり、大統領は原爆の投下を包括的に承認しており、個別の投下指示は軍の判断に委ねられていた。目標の選定、タイミング、順序、投下の判断はすべて軍の手にあった。
実際に誰が「長崎」への投下を決めたのか?
原爆投下の作戦運用を担ったのは、以下の人物たちである。
| 名前 | 役職 | 主な役割 |
|---|---|---|
| レスリー・グローヴス | 陸軍准将/マンハッタン計画責任者 | 科学開発と兵器引き渡しの統括 |
| トーマス・T・ハンディ | 陸軍 参謀総長代行 | 原爆投下命令書の署名者 |
| カーティス・ルメイ | 第21爆撃集団司令官 | 実際の作戦(509部隊)指揮 |
当初の2発目の目標は「小倉」だったが、当日の天候と煙による視界不良のため、小倉上空での投下は断念され、長崎へ変更された。この判断も、現場の軍部(特に投下機「ボックスカー」の乗員および指揮官)によるものだ。
原爆投下を支持・容認した高官たち
| 氏名 | 当時の役職 | 発言・立場 | 根拠・出典 |
|---|---|---|---|
| ハリー・S・トルーマン | 米国大統領 | 「アメリカ人の命を救うために最善の選択だった」 | 回想録および大統領日記 |
| ヘンリー・スティムソン | 陸軍長官(戦争担当) | 「投下により戦争を早期終結できた。正当だった」 | 論文 “The Decision to Use the Atomic Bomb”(Harper’s, 1947) |
| ジョージ・マーシャル | 陸軍参謀総長 | 「軍事的選択肢の一つとして理解されるべき」 | 複数の回顧録資料に基づく |
| カーティス・ルメイ | 第21爆撃集団司令官(東京大空襲主導) | 「原爆がなくても日本は降伏しただろうが、戦争終結の一手段だった」 | 記録インタビュー |
| レスリー・グローヴス | マンハッタン計画責任者(陸軍工兵) | 「原爆は戦争を終わらせるための必要な兵器だった」 | 証言・回想録『Now It Can Be Told』 |
原爆投下に疑問・反対を示した米軍高官たち
| 氏名 | 当時の役職 | 発言・立場 | 根拠・出典 |
|---|---|---|---|
| ドワイト・D・アイゼンハワー | 欧州連合軍最高司令官(のち大統領) | 「日本はすでに降伏寸前であり、このような恐ろしい兵器を使う必要はない」 | 回想録『Mandate for Change』 |
| ダグラス・マッカーサー | 太平洋方面連合軍司令官 | 「原爆は必要なかった。日本は和平を模索していた」 | William Manchester著『American Caesar』 |
| チェスター・ニミッツ | 太平洋艦隊司令長官 | 「軍事的に見て、原爆は決定打ではなかった」 | Gar Alperovitz『The Decision to Use the Atomic Bomb』 |
| ウィリアム・リーヒ | 大統領首席軍事顧問、元海軍作戦部長 | 「原爆は必要なかった。日本人はすでに敗北しており、飢餓と爆撃で降伏寸前だった」 | 自著『I Was There』 |
| トーマス・T・ハンディ | 陸軍副参謀総長(実際の原爆投下命令署名者) | 「使用を政治的に疑問視する声も理解できる」 | 記録・回想録(諸資料) |
| ルイス・ストローズ | 原爆政策に関与した海軍高官 | 「日本への最初の原爆投下は必要だったとしても、2発目(長崎)は不必要だった」 | スピーチ記録 |
| フランク・レポートの科学者たち | マンハッタン計画・シカゴ大学の科学者 | 「使用は国際的非難を招き、実験的公開が望ましい」 | 『The Franck Report』(1945年6月) |
一部は「限定的賛成」や「後悔」の立場も
| 氏名 | 備考 |
|---|---|
| ルメイ将軍 | 軍事的には「原爆は不要」とも述べているが、任務として遂行 |
| ハリー・S・トルーマン米国大統領 | 長崎への2発目投下には、「二発目は知らされていなかった」と不快感を示した記録もある |
| グローヴス准将 | 戦後は原爆の政治的影響の大きさに懸念を持っていた |
トルーマンは2発目を知らなかった?
トルーマンが1945年8月10日に「これ以上の原爆投下は、私の明示的な許可がなければ実施してはならない」と命じた。 これは、日本の降伏が迫る中、さらなる民間人の犠牲を回避するため、大統領が自ら原爆使用の最終決定権を掌握した重要な指示だった。
当時の閣議での大統領の発言や、それを受けた関係者のメモを通じて確認されている。
主要な情報源
- ヘンリー・ウォーレス商務長官の日記
ウォーレスは、1945年8月10日の日記に、トルーマン大統領が閣議で「原子爆弾の投下を中止するよう命令した」と述べたことを記録している。大統領は「さらに10万人、特に子どもたちを皆殺しにするのはあまりにも恐ろしい」と感じたと記されている。 - ジョージ・C・マーシャル陸軍参謀総長の手書きメモ
マンハッタン計画責任者のレズリー・グローブス少将が、次の原爆が8月17日か18日には投下可能であると報告したメモに対し、マーシャル参謀総長が手書きで「1945年8月10日。大統領からの明示的な許可なくして日本に投下してはならない。」と書き加えている。
コミュニケーションのギャップ
- 2発目の爆弾は、最初の投下からわずか3日後の8月9日に投下された。この短い期間で、大統領がワシントンD.C.から、太平洋のテニアン島で準備が進む作戦の細部まで逐一報告を受けていた可能性は低い。
- 広島の被害状況に関する詳細な報告すら、長崎への投下の直前または直後までトルーマンのもとには届いていなかった。
| 日付 | 出来事 | トルーマンへの報告内容 |
|---|---|---|
| 1945年 8月6日午前8時15分 | 広島に原爆投下 | 数時間後、トルーマンに「目標に対し投下成功」と電報で報告 |
| 8月6日午後 | トルーマン、公式声明を発表 | 「これは終戦を早める手段であり、米兵の命を救うためである」と発表 |
| 8月7日 | 広島の被害概要が届き始める | 「都市が破壊された」と報告されるが、死傷者数などの詳細は不明 |
| 8月9日午前11時02分 | 長崎への2発目投下(小倉断念後) | 長崎投下時点で、トルーマンは広島の被害実態までは把握していなかった |
原爆投下に責任は誰にあるのか?
この構造から分かることは、大統領の責任と軍の判断が分離していたという事実だ。
- トルーマン:包括的に投下を許可(対象都市は知らされていたが、タイミングには介入せず)
- 軍部:命令を受けて即時実行。広島 → 小倉断念 → 長崎という流れで投下
- トルーマンの反応:2発目投下に驚き「大統領の許可なしに今後使用不可」と指示
8月6日の広島原爆投下より前に日本が降伏する状況だったか、あるいはソ連参戦によって降伏を真剣に考え始めたかについては、歴史学者の間でも議論が分かれる複雑な問題だ。
トルーマンが原爆投下を選んだ理由
トルーマンが原爆投下を決断した理由は、単純な一つではなく、複数の政治・軍事的要因が絡んでいる。以下に当時の公式発言や日記、米国政府の記録に基づく実際の理由を、整理する。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 日本の早期降伏 | 1945年春~夏、日本は依然として「本土決戦」の構え。原爆は短期間で戦争を終わらせる手段とされた。 |
| アメリカ兵士の犠牲回避 | 「本土侵攻では50万~100万人の米兵死傷」と試算。米軍の犠牲を減らすために原爆が選ばれた。 |
| 対ソ連への牽制 | ソ連参戦前に降伏させ、東アジアにおけるソ連の影響拡大を阻止する狙いも指摘されている。 |
| 開発した兵器の使用圧力 | 約20億ドルかけたマンハッタン計画。「使わなければ無駄になる」との技術者・軍部からの圧力も存在した。 |
トルーマン本人の公式発言・日記から
- 7月25日の日記(ポツダム会談中) “I have told the Secretary of War to use it so that military objectives and soldiers and sailors are the target and not women and children.”
→ 「軍事目標と兵士・水兵を狙うべきであり、女性や子供は標的にしてはならない」 - 8月6日の声明(広島投下後の公式発表) “We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans.”
→ 「我々は戦争の苦しみを短縮し、何千何万もの若いアメリカ人の命を救うために原爆を使用した」
実際には民間人が主な犠牲者だった
- 軍事施設を狙ったとはいえ、広島・長崎の都市構造上、被害者の大半は民間人だった。
- トルーマンも投下後、被害報告に接して「これ以上は子供たちを殺すことはできない」と述べたとされる(副大統領だったヘンリー・ウォレスの日記による)。
一部指摘される「建前」と「本音」
| 建前(公式理由) | 戦争終結・米兵保護 |
|---|---|
| 本音(戦略的意図) | 対ソ牽制・新兵器の実戦テスト |
実際のところ、「兵士保護」は正しいが、ソ連参戦の前倒しや新兵器効果の誇示も重要な動機だったと分析する歴史学者は多い。
トルーマンの原爆投下理由
- 日本降伏の短期化と米兵保護(最優先の理由)
- 対ソ連戦略と政治的プレッシャー(副次的理由)
- 新兵器の実戦利用という軍部圧力(背景理由)
日本は原爆投下前、降伏を考えていたのか
8月6日より前に日本は降伏する状況だったか?
客観的に見れば、1945年夏には日本の敗戦は必至の状況だった。
- 本土への空襲: 日本の主要都市は絨毯爆撃によって壊滅的な被害を受け、生産能力は著しく低下。
- 海上封鎖: 連合国による海上封鎖で資源が枯渇し、食糧事情も悪化。
- 沖縄戦の敗北: 沖縄戦での甚大な被害は、本土決戦の困難さを如実に示した。
- ドイツの降伏: 1945年5月には同盟国ドイツが降伏し、日本は完全に孤立。
しかし、当時の日本政府、特に軍部は「国体護持(天皇制の維持)」を絶対条件とし、それ以外の無条件降伏は受け入れがたいと考えていた。そのため、ポツダム宣言(7月26日発表)に対しても、鈴木貫太郎首相は記者会見で「黙殺」という態度を示した。これは、裏でソ連を仲介役とした和平交渉を進める意図があったためだが、連合国側には「拒否」と受け取られ、原爆投下への口実を与えてしまった側面がある。
政府内部では、一部の外務省関係者や重臣(東郷茂徳外相など)はポツダム宣言の受諾やむなしと考えていたが、陸軍は徹底抗戦を主張し、意見が対立していた。
8月9日のソ連参戦によって降伏を真剣に考え始めたか?
ソ連参戦は、日本の降伏決定に決定的な影響を与えた主要因の一つと見なされている。
- ソ連仲介の終戦工作の頓挫
日本は、日ソ中立条約を盾にソ連を仲介役として終戦交渉を進めようと画策していた。日本政府のこの「最後の望み」は、ポツダム宣言にも記載されていたソ連の対日参戦によって完全に絶たれた。ソ連が突如として満州に侵攻し、あっという間に日本の関東軍を崩壊させたことは、日本政府に大きな衝撃を与えた。 - 国体護持の危機感
陸軍は本土決戦を主張していたが、ソ連の参戦によって、日本本土へのソ連軍の侵攻や、ソ連が共産主義革命を日本にもたらし、天皇制が完全に破壊されるという危機感が現実のものとなった。アメリカが天皇制維持について明言しない中、ソ連の介入は「国体」そのものの存続を脅かすと考えられた。 - 御前会議での「聖断」
8月9日、長崎への原爆投下とソ連参戦の報が重なる中で開かれた御前会議では、軍部の徹底抗戦論と外務省のポツダム宣言受諾論が激しく対立し、議論は膠着した。最終的に、昭和天皇が「これ以上国民を苦しめることは忍びがたい」としてポツダム宣言受諾を「聖断」した。
歴史の複雑さを直視する
「原爆投下=トルーマンが直接命令した」という単純な図式では、歴史の全体像を見誤る。
責任の所在は明確だが、意思決定のプロセスは軍事的・政治的に非常に複雑で、通信のタイムラグや判断の即時性も関与していた。
広島・長崎という悲劇の裏にある構造を知ることは、今後の戦争と政治に対する我々の理解を深める第一歩になるだろう。