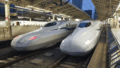敵国条項の歴史
国連憲章の敵国条項(第53条および第107条)は、第二次世界大戦の終結直後、1945年に制定された。これは、戦勝国である連合国が、敗戦国が将来にわたり再び侵略行為を行うことを防ぐために、過渡的な措置として設けられた。
旧枢軸国の一覧は以下の通りだ。
| 国名 | 説明 |
| 日本 | 1940年に日独伊三国同盟を結び、枢軸国の一員として参戦した。 |
| ドイツ | 枢軸国の中心的存在であり、イタリアや日本と共に連合国と戦った。 |
| イタリア | 初期の枢軸国の一員であり、ムッソリーニの指導の下でドイツと協力した。 |
| フィンランド | ソ連との戦争においてドイツと協力したため、事実上枢軸国側に立たされたが、正式な同盟国ではなかった。 |
| ハンガリー | 1941年にドイツの圧力を受けて枢軸国に加わり、主に東部戦線で戦った。 |
| ルーマニア | 1940年に枢軸国に参加し、ドイツと共にソ連に侵攻した。 |
| ブルガリア | 1941年に枢軸国に加わり、主にバルカン半島での戦闘に参加した。 |
| タイ | 日本と同盟を結び、枢軸国側で戦った国の一つである。 |
敵国条項とその解説
敵国条項は、第二次世界大戦中の敵国に対して、安全保障理事会の許可なく、国連加盟国が強制行動をとることを可能にする内容である。
- Article 53
- The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state. (安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、この種の地域的取極又は地域的機関を利用する。ただし、安全保障理事会の許可がない限り、いかなる強制行動も、地域的取極又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国に関する措置で、第百七条に従って規定されるもの又はその敵国における侵略政策の再現に備えることを目的とする地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基き、この機構がその国家による一層の侵略を防止する責任を負うときまで、この限りでない。)
- The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter. (本条1で用いる「敵国」という語は、第二次世界大戦中に今次憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。)
- Article 107
Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action. (第二次世界大戦中に今次憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に関する行動で、その戦争の結果として、その行動について責任を有する政府がとった又は許可した行為は、今次憲章のいかなる規定も、これを無効にし、又は排除するものではない。)
なぜ敵国条項は無効化されているのか
国連憲章には、すべての加盟国は主権平等の原則に基づき行動すると定めた第2条第4項がある。
- Article 2
All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. (すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。)
日本やドイツが1950年代に国連に加盟したことで、これらの国も第2条第4項の保護下に置かれた。この結果、特定の加盟国を差別的に扱う敵国条項は、憲章の根本原則と矛盾することとなり、実質的に効力を失っていると解釈されている。
「日本が核武装したら敵国条項で攻撃される」という指摘の誤り
かつて国会で指摘された「日本が核武装したら、敵国条項で攻撃される」という主張は、根拠が正しいとは言えない。
- 敵国条項は対日適用外: 前述の通り、日本が国連加盟国であるため、敵国条項は既に実質的に無効化されている。
- 攻撃の法的根拠: 仮に日本が核兵器を保有しようとした場合、それは敵国条項ではなく、核兵器不拡散条約(NPT)などの国際法違反として扱われる。この場合、国連安全保障理事会が付託を受け、経済制裁などの措置を検討するのが国際的な手続きである。
- 軍備と攻撃: 日本の軍備増強自体が、国連憲章上、他国から攻撃される直接的な理由とはならない。武力行使は、憲章第7章や第51条に基づく自衛権の行使など、特定の条件下でのみ正当化される。
第7章:平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第7章は、国際平和と安全を回復するための集団的措置について定めている。
- Article 39: The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security. (安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。)
- Article 41: The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations. (安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を講ずべきかを決定することができ、また、国際連合加盟国に対し、その措置を適用することを要請することができる。この措置には、経済関係、鉄道、航路、航空、郵便、電信、無線電信その他の交通運輸通信手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶が含まれる。)
- Article 42: Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations. (安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと判断し、又は不十分であったと判断したときは、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。その行動には、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動が含まれる。)
第51条:自衛権
第51条は、個別的または集団的自衛権について定めている。
- Article 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. (この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合に、安全保障理事会が国際の平和及び安全を維持するために必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使にあたって加盟国がとる措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を維持し又は回復するために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基づく権能及び責任に、いかなる形でも影響を及ぼすものではない。)
日本が核武装したら
日本が核武装した場合、まずIAEA(国際原子力機関)が調査し、違反が確認されると国連安全保障理事会に付託され、経済制裁などの措置がとられる。
制裁のプロセス
- IAEAによる調査: 日本が核兵器を開発しているとの疑いが生じた場合、IAEAが査察を実施する。日本は核兵器不拡散条約(NPT:米、露、英、仏、中の5か国を「核兵器国」と定め「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止する条約)の加盟国であり、IAEAの査察を受け入れる義務があるため、違反が認定されれば国際社会からの信頼を失う。
- 安保理への付託: IAEAが違反を認定すると、問題は国際の平和と安全への脅威として国連安全保障理事会に付託される。
- 安保理による制裁: 安保理は、核開発を停止させるために、経済制裁(武器禁輸、金融取引の制限など)や外交的圧力といった措置を決定する。
現在、制裁を受けている国と組織
国連安全保障理事会が現在、制裁を課している主な国と組織は以下の通りである。
| 国名/組織名 | 制裁理由 | 主な制裁内容 |
| 北朝鮮(DPRK) | 核・ミサイル開発 | 武器禁輸、金融制裁、渡航禁止、資産凍結、特定の物資の輸出入禁止など |
| イラン | 核開発活動 | 武器禁輸、資産凍結、渡航禁止など |
| タリバン、ISIL(ダーイシュ)、アル・カーイダ | テロ活動 | 資産凍結、渡航禁止など |
| ソマリア | 平和と安全を脅かす行為、武器流入 | 武器禁輸、渡航禁止、資産凍結など |
| コンゴ民主共和国 | 平和と安全を脅かす行為、武器流入 | 武器禁輸、渡航禁止、資産凍結など |
| スーダン | ダルフール紛争 | 武器禁輸、渡航禁止、資産凍結など |
| イラク | テロ組織への支援 | 武器禁輸、資産凍結など(一部解除) |
| リビア | 内戦、平和と安全を脅かす行為 | 武器禁輸、渡航禁止、資産凍結など |
| 中央アフリカ共和国 | 平和と安全を損なう行為 | 武器禁輸など |
| マリ | 平和と安全を脅かす行為 | 渡航禁止、資産凍結など |
| 南スーダン | 平和を脅かす行為 | 武器禁輸、渡航禁止、資産凍結など |
| イエメン | 平和と安定を脅かす行為 | 武器禁輸、渡航禁止、資産凍結など |
| ハイチ | ギャングによる暴力、人権侵害 | 武器禁輸、渡航禁止、資産凍結など |
敵国条項が削除されない理由
敵国条項が削除されない最大の障壁は、国連憲章の改正手続きの困難さにある。
- 改正手続きの厳格さ: 憲章改正には、国連加盟国の3分の2の賛成に加え、安全保障理事会の全常任理事国(アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国)の批准が必要となる。
- 常任理事国の思惑: 敵国条項の削除は、安保理の常任理事国数の増加といった、より広範な憲章改革の議論につながる可能性が高い。特にロシアや中国は、安保理の構成が変わることで自国の影響力が低下することを懸念しており、このような改正には同意しない可能性が高い。
そのため、敵国条項は多くの国がその削除を望んでいるにもかかわらず、政治的な対立や手続き上の問題から、削除されないまま現在に至っている。