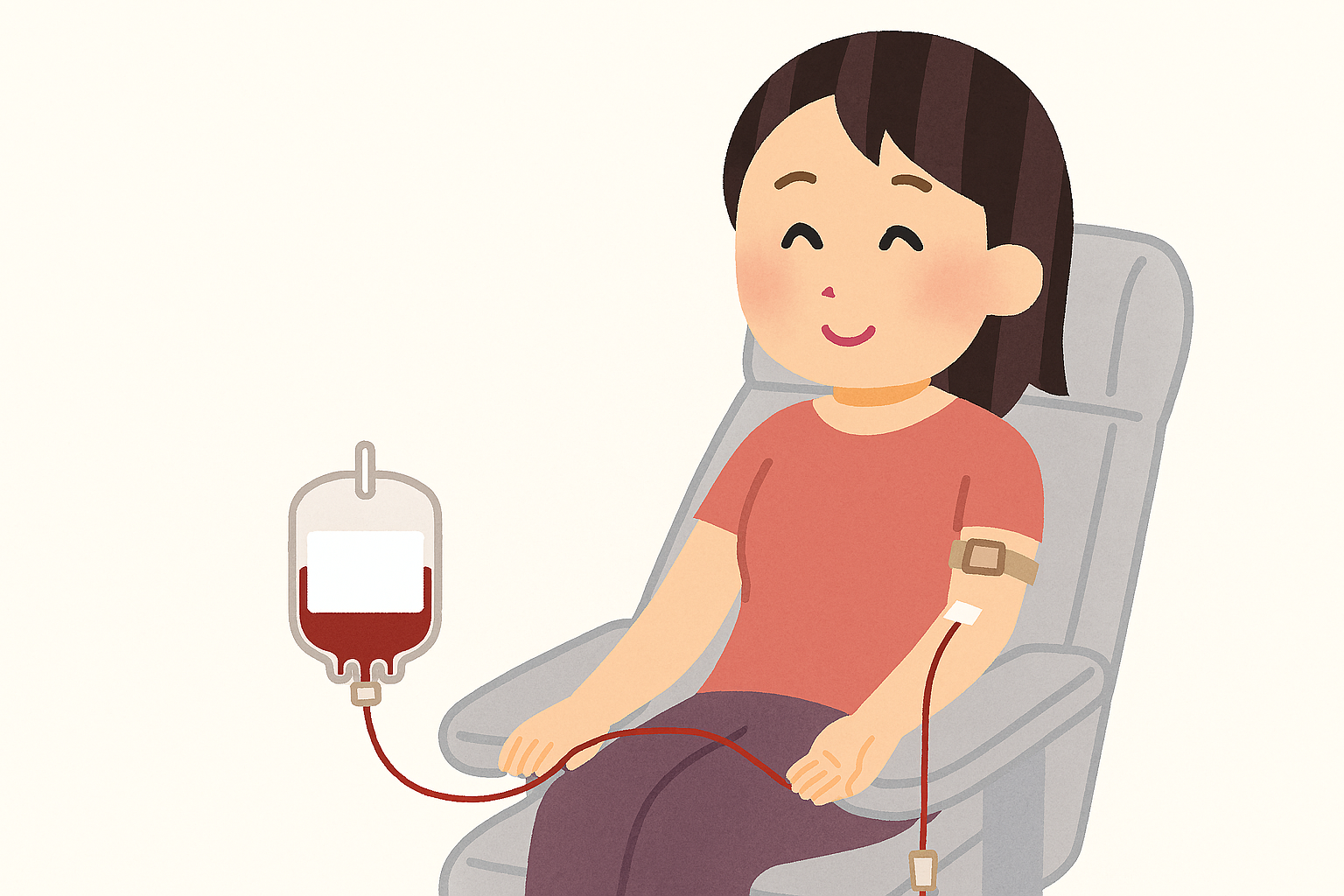スウェーデンの移民政策
スウェーデンは近年、移民政策の根本的な見直しに踏み切った。かつては人道主義の象徴とされ、難民受け入れに積極的だったが、現在は「秩序ある帰還」を掲げて制度設計の再構築を進めている。この転換は排除を目的としたものではなく、移民政策上にある問題点の可視化と理念の再定義に基づく構造的な対応と捉えるべきである。
最大約490万円の帰還手当(2024年発表)
スウェーデン政府は2024年、帰還手当を最大35万スウェーデン・クローナ(約490万円)に引き上げる方針を発表した。従来の1万クローナから約35倍の増額となる。対象は滞在資格のない移民や庇護申請が却下された者などであり、理念と運用の整合性を重視した政策の一例といえる。
通報義務の検討と制度運用の厳格化(2024年〜2025年)
医療機関や教育現場を含む関係者に対し、滞在資格のない移民の通報義務を課す法改正が検討されている。2025年時点で議論は継続中であり、統合支援よりも選別と排除に軸足を移した政策転換が鮮明になってきた。
労働移民に対する選別と理念の再定義(2024年以降)
労働移民には「月収中央値の80%以上の給与」が求められ、低賃金労働者の流入を制限する方向へ。民主的価値観を共有できる者のみを受け入れるという姿勢が制度設計の納得性を高めている。
統合失敗と政治的転換が背景にある
2015年のシリア難民大量流入以降、社会統合の失敗、治安悪化、福祉制度の圧迫が顕在化した。2022年の右派政権誕生を契機に、移民政策は理想主義から現実主義へと転換した。2024年には50年ぶりに「移出民が移入民を上回る」見通しとなっており、難民増加による問題を放置せず再設計に踏み切った点は注目に値する。
類似政策を採用する他国の事例(2025年時点)
以下は、スウェーデンと同様に制度疲労に向き合い、移民政策を再設計している主要国の比較表になる。
類似政策の比較表(2025年)
| 国名 | 主な施策内容 | 制度理念の特徴 | 根拠・日付 |
|---|---|---|---|
| デンマーク | 帰還センター設置、福祉制限、統合契約制度 | 共生のための厳格さ | JCone報告(2023年11月) |
| フランス | 自発的帰国支援、統合失敗の統計分析、暴動後の制度再設計 | 社会的摩擦を契機とした再構築 | Le Monde(2023年7月) |
| ドイツ | 「ターボ帰化」制度の廃止、家族呼び寄せの一時停止 | 統合の質を重視した制度再設計 | JILPT(2025年7月) |
近年来日した外国人と在日韓国・朝鮮・中国人の違い
日本社会では「外国人」や「在日」という言葉がしばしば混同されて使われる。しかし、社会的背景を踏まえると、近年来日した外国人と在日韓国・朝鮮・中国人(戦前・戦後定住者)は、まったく異なる存在である。
概念の違い:定住と滞在、歴史と制度
- 在日韓国・朝鮮・中国人は、主に戦前・戦後(1952年: サンフランシスコ講和条約発効により、日本国籍を正式に喪失)の歴史的経緯により日本に定住した人々とその子孫。多くは日本生まれ・日本育ちであり、社会的には日本人と同様の生活を営んでいる。
- 一方、近年来日した外国人は、技能実習、特定技能、留学、就労などの制度に基づき、短期または中期的な滞在を前提として来日している。制度上は「一時的滞在者」として扱われ、帰国前提の設計が多い。
この違いは、在留資格、法的地位、社会的定着度、制度目的において明確である。
制度的・歴史的な違いの整理
| 区分 | 来日外国人(近年) | 在日韓国・朝鮮・中国人(戦前・戦後定住者) |
|---|---|---|
| 主な在留資格 | 技能実習、特定技能、留学、就労、家族滞在など | 特別永住者、永住者、定住者など |
| 入国時期 | 2000年代以降が中心 | 多くは戦前・戦後に渡日し、定住化 |
| 国籍 | 外国籍(ベトナム、ミャンマー、フィリピン等) | 外国籍だが、日本生まれ・日本育ちが多数 |
| 在留管理 | 入管法に基づく更新・審査が必要 | 特別永住者は更新不要、強制退去の対象外 |
| 帰国可能性 | 一時的滞在が前提、帰国前提の制度も多い | 実質的に日本社会に定着している |
| 社会的摩擦 | 制度疲労による失踪・不法就労が課題 | 犯罪率は低く、社会的摩擦は限定的 |
日本の制度疲労と納得性の欠如
日本の技能実習制度や特定技能制度は、制度疲労が顕在化しているにもかかわらず、理念の再定義がなされていない。「移民ではない」という建前と「労働力確保」という実態の乖離が、制度の納得性を損なっている。
技能実習制度の実態—送出国と失踪者の国籍(2025年)
法務省の統計(令和6年:2024年)によれば、技能実習生の主な送出国と失踪者数は以下の通り。
技能実習生の送出国・失踪者数(上位5か国)
| 国名 | 技能実習生数(推定) | 失踪者数 | 失踪率 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム | 約40,000人以上 | 3,865人 | 1.5% | 最多の送出国、失踪者数も最多 |
| ミャンマー | 約40,371人 | 1,263人 | 3.1% | 緊急避難措置の見直し後も高水準 |
| インドネシア | 約30,000人前後 | 520人 | 0.5% | 失踪率は比較的低い |
| 中国 | 約20,000人前後 | 335人 | 0.9% | 減少傾向 |
| カンボジア | 約15,000人前後 | 275人 | 1.5% | 送出機関の停止措置あり |
参照: 法務省「技能実習生の失踪者数の推移」(2025年5月)
失踪者の多くは、来日前に高額な費用を負担しており、実習先での賃金未払い・人権侵害などが原因で失踪に至るケースが多い。制度設計上、「技能移転による国際貢献」という理念と、「低賃金労働力の供給源」という実態が乖離しており、納得性の低さが制度疲労を加速させている。
難民受け入れ制度とクルド人の現状
日本の難民受け入れの全体像(2024年)
- 難民申請者数: 13,823人(前年比266%増)
- 難民認定者数: 303人(認定率 約2.2%)
- 補完的保護対象者: 2人(新制度に基づく)
- 人道的配慮による在留許可: 1,005人
- 主な申請国籍: スリランカ、トルコ(クルド人含む)、パキスタン、インド、カンボジアなど
日本の難民認定制度は、国際的に見ても認定率が極めて低く、制度疲労と理念の乖離が顕著に表れている。2024年の難民申請者数は13,823人に達し、前年比266%増となったが、認定されたのは303人(認定率約2.2%)にとどまる。補完的保護制度の導入もあったが、2024年時点での認定者はわずか2人に過ぎない。
クルド人はその象徴的な存在である。主にトルコ出身で、民族的・政治的迫害から逃れて来日しているが、日本では難民として認定されることはほとんどない。埼玉県川口市などにコミュニティが形成されているが、在留資格の不安定さや就労制限、地域との摩擦が課題となっている。
難民の出身階層は多様
| 層 | 特徴 | 例 |
|---|---|---|
| 政治・知識エリート | 政権批判や民主化運動に関与し、迫害対象となる | ジャーナリスト、弁護士、大学教授、元官僚など |
| 中間層 | 教育水準はあるが、民族・宗教・性的指向などで差別される | 教師、看護師、商人など |
| 貧困層・農村部 | 紛争や民族浄化の被害を直接受けるが、情報や資源に乏しい | 農民、労働者、無職者など |
日本政府によるステルス移民政策:育成就労制度と特定技能制度の拡張(2027年〜)
- 育成就労制度(2027年4月開始予定) 技能実習制度を発展的に廃止し、外国人労働者の育成と定着を目的とする新制度。原則3年の在留期間を経て、特定技能1号・2号への移行を前提とする。
- 特定技能制度の拡張(2024年閣議決定) 特定技能1号の受け入れ見込み数が最大82万人に再設定。対象分野は16分野に拡大され、外食、宿泊、農業、漁業、介護、製造業などが含まれる。 特定技能2号では在留期間の上限なし・家族帯同・永住申請可能という定住ルートが制度化されている。
制度設計上の問題点
- 理念と実態の乖離 政府は「移民政策ではない」と繰り返すが、制度的には永住・家族帯同・無期限在留が可能であり、実質的な移民政策と同等の構造を持つ。
- 定住人口の急増リスク 82万人の受け入れに加え、家族帯同を含めると100万人規模の定住人口増加が予測される。これは地域社会・教育・医療・治安・福祉制度に直接影響を与える。
- 送り出し国の変化 円安とアジア圏の人材確保難により、アフリカ諸国やイスラム圏が新たな供給源として注目されている。文化的・宗教的摩擦のリスクも高まる。
- 制度疲労の加速 技能実習制度で顕在化した失踪・人権侵害・納得性の欠如が、制度名を変えて再生産される可能性がある。理念の再定義なしに制度を拡張することは、制度疲労の構造的再発を招く。
制度設計は理念と現場の架け橋である
スウェーデンの移民帰還政策は、移民政策の問題点を可視化し、理念と現場の乖離を埋める試みといえる。移民排除の論理に陥るリスクはあるが、日本の現状よりも一歩先を行っている。制度は理念の体現であり、現場の納得なくして持続可能性はない。