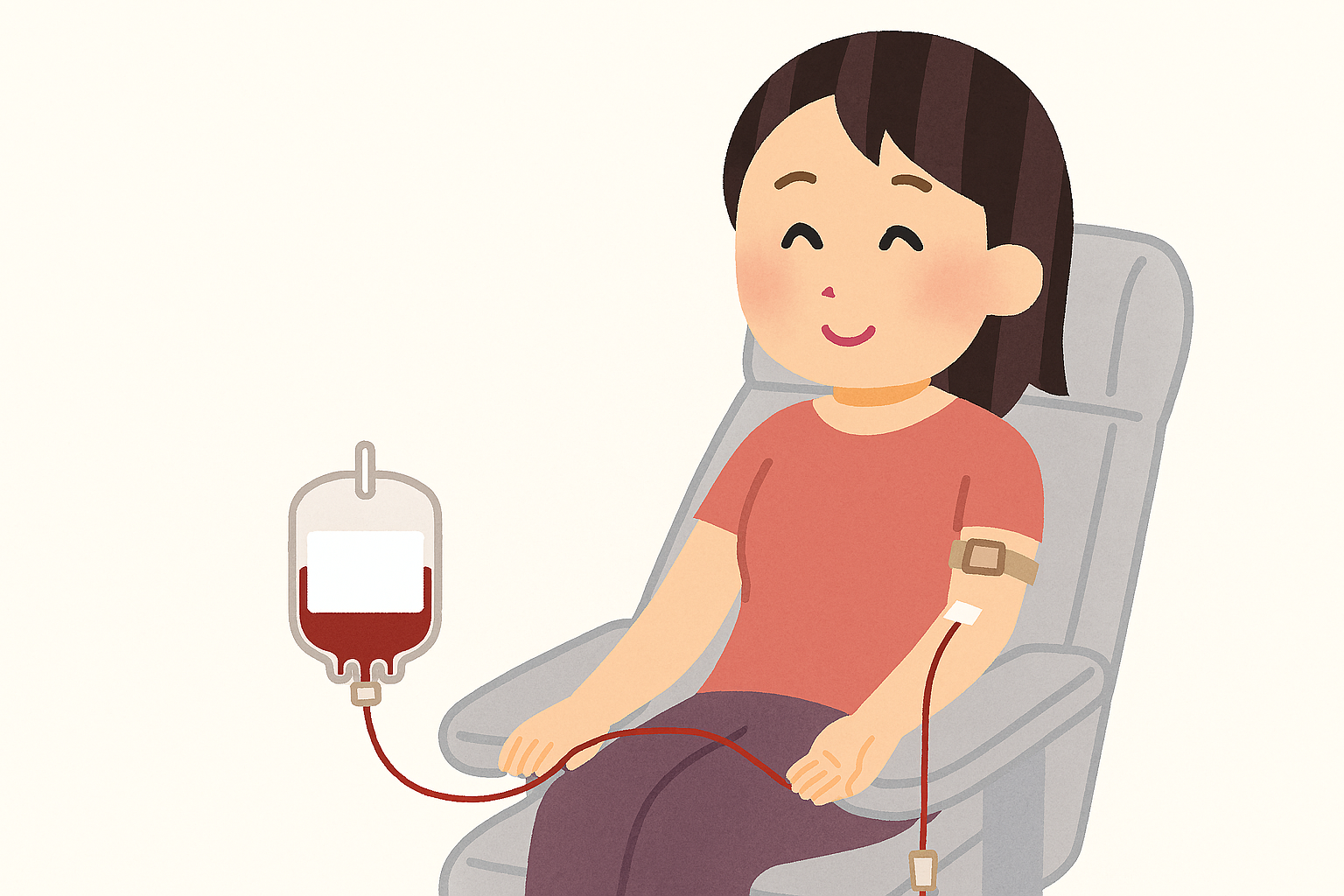はじめに
近年、日本における献血者数と献血量は減少傾向にある。一方で、高齢化の進行や医療技術の高度化により、血液製剤の需要は増加している。
このままでは、安定的な血液供給体制の維持が困難になる可能性が高く、制度的対応が急務となっている。
献血は、無償の善意によって支えられる公共活動の代表例である。
だからこそ、国家がその貢献に対して名誉を与える制度を再設計することは、公共心の育成と誇りの継承に直結する。
献血の歴史と課題を振り返り、国家顕彰の意義と再設計案、そして海外事例との比較を通じて、制度のあり方を考察する。
血液銀行と売血制度の歴史
1951年、大阪で「日本ブラッドバンク」が開業。
保存血輸血のために、あらかじめ採血しておいた血液を保存・供給する民間機関であり、民間企業が血液を買い取り、医療機関に販売する商業モデルだった。
1950年代には、200ccの血液が400円~550円程度で買い取られていた。
この価格は、当時の生活水準から見ても決して小さくない。昭和30年頃の大学卒業者の初任給は約8,000〜10,000円であり、550円はその約5〜7%に相当する。
現在の初任給を25万円と仮定すれば、1回の売血で約12,500〜17,500円を得ていた計算になる。
この売血制度が健康被害の拡大を招いた。
貧困層や日雇い労働者が現金収入を得る手段として頻繁に売血を行い、貧血や肝炎などの健康被害が多発。「黄色い血」と呼ばれる赤血球の少ない質の悪い血液が社会問題となった。
1964年、駐日米国大使ライシャワーが刺傷事件後の輸血で肝炎に感染。
この事件が売血制度の危険性を広く知らしめる契機となり、社会的な議論が加速した。
同年、政府は「献血の推進について」を閣議決定。
1974年には民間血液銀行が売血制度を完全廃止し、以後は輸血用血液をすべて献血で賄う体制へと移行した。
現在、日本では売血は禁止されており、献血は無償で行われる。
かつては金券(図書券など)が記念品として渡されていたが、2002年の「血液法」施行以降は禁止され、現在は食品や飲料などが提供されている。
最近10年間の献血者数・献血量・血液供給の推移
| 年度 | 献血者数(万人) | 献血量(万本) | 血液製剤供給量(万本) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 約520 | 約1,050 | 約1,020 |
| 2018 | 約510 | 約1,030 | 約1,000 |
| 2020 | 約495 | 約1,000 | 約980 |
| 2022 | 約490 | 約980 | 約960 |
| 2024 | 約501(全血342+成分158) | 約970 | 約950 |
献血者数・献血量ともに緩やかな減少傾向にあり、特に若年層の献血率が低下している。
医療機関への供給量も減少傾向で、需要は横ばい〜微増。将来的な供給不足が懸念される。
献血表彰・顕彰の再設計案
国家による顕彰として統一し、段階的に表彰レベルを設けることで、公共性の明確化と誇りの醸成を図る。以下に、献血表彰・顕彰の再設計案を示す。
| 区分 | 対象 | 表彰内容 | 授与主体 |
|---|---|---|---|
| 青章 | 献血10回以上 | 感謝状+記念品 | 厚生労働省 |
| 銀章 | 献血30回以上 | 表彰状+記章 | 厚生労働省 |
| 金章 | 献血70回以上 | 表彰状+記章 | 厚生労働省 |
| 紫章 | 献血100回以上 | 勲章+内閣府感謝状 | 内閣府 |
マイナンバー連携によるデジタル勲章制度を導入し、履歴証明として活用可能にする。このようなことで、公共活動が文化として根づく。
海外の献血表彰制度
公共活動に対する国家顕彰は、日本だけでなく世界各国でも制度化されている。以下に、各国の献血表彰制度をまとめる。
各国の献血表彰制度一覧
| 国 | 制度名・主体 | 表彰対象の回数・基準 | 表彰内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 献血有功章制度 | 30回、50回、100回、200回、300回 | 記章(銀章、金章、名誉章など)、感謝状 | 献血運動への貢献度が高い団体・個人には大統領表彰も授与される。 |
| フランス | フランス血液事業団(EFS)による表彰 | 明確な回数基準は非公開 | ディプロマ(証書)、メダル | 国家功労勲章は献血回数のみでなく、総合的な功績で判断される。 |
| アメリカ | アメリカ赤十字 Milestone Recognition Program | 1ガロン(約3.785L)ごとの節目 | ピンバッジ、証明書、記念品 | 献血量を「ガロン」単位で集計する点が特徴。 |
| ベルギー | 赤十字主導の地域表彰制度 | 明確な回数基準なし | 学校や地域イベントでの表彰、記念品 | 若年層への献血推進が盛んで、教育機関との連携が強い。 |
| 台湾 | 台湾血液基金会によるキャンペーン | 明確な回数基準なし | 総統や著名人による表彰、広報への起用 | 国家を挙げて献血活動を推進しており、総統自らが広告塔となる。 |
| ドイツ | ドイツ赤十字による表彰制度 | 回数に応じた段階的な基準 | 地域イベントでの表彰、ピンバッジなどの記念品 | 売血制度が合法である一方、無償献血に対するボランティア意識も高い。 |
| シンガポール | HSA(保健科学庁)・赤十字による表彰 | 回数に応じた段階的な基準(Medal for Life等) | SNSやアプリを通じたデジタル表彰、メダル | デジタルツールを積極的に活用した先進的な広報・表彰制度を展開。 |
| イギリス | NHS Blood and Transplant Donor Recognition Scheme | 10回、25回、50回、75回、100回、250回など | デジタルバッジ、記念カード、ピンバッジ、記念品(100回以上は式典招待) | デジタルとリアルの両方で |