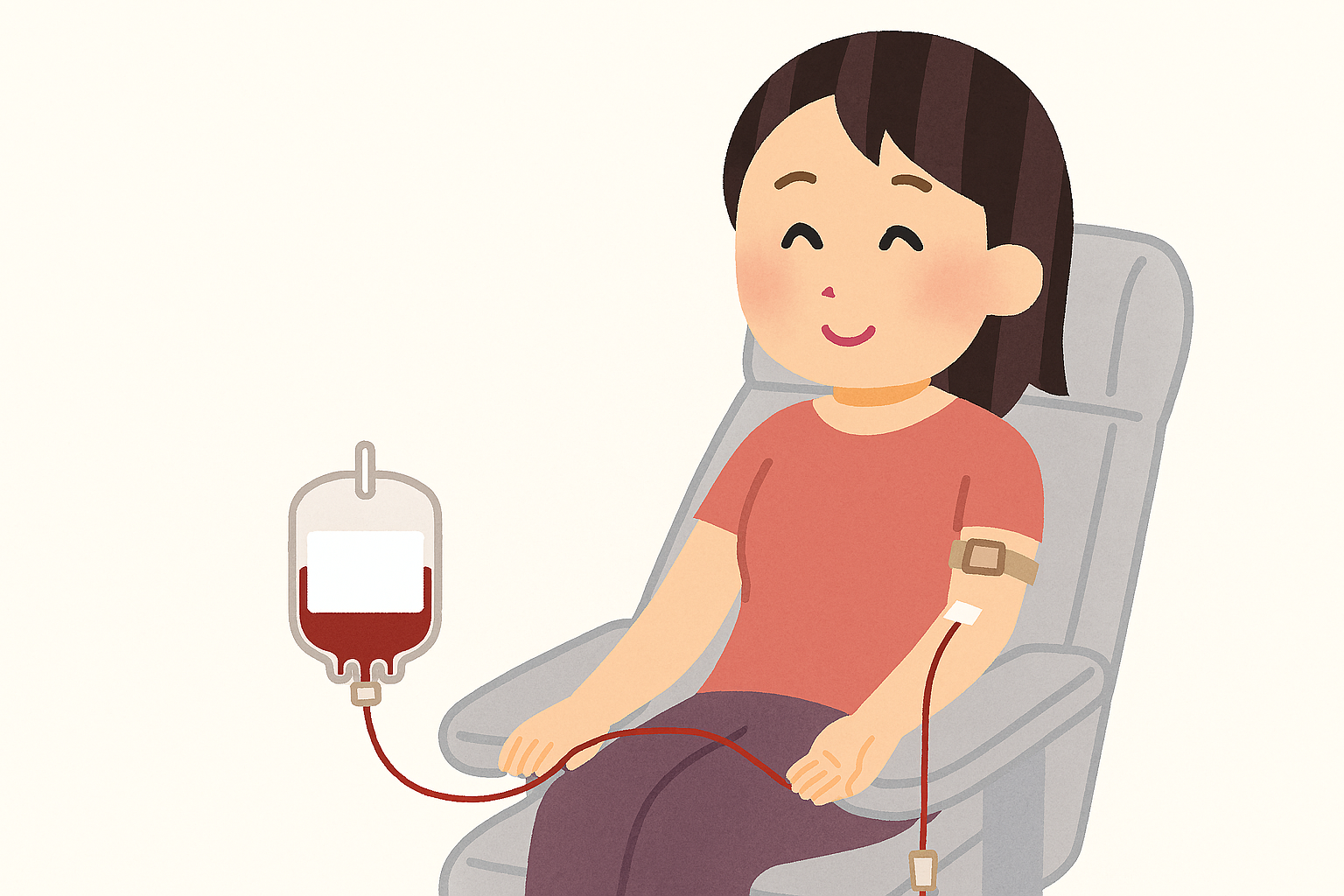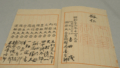事件事例:教員が児童・生徒から暴力を受けたケース
文科省統計:精神疾患による教員の病気休職(2023年度)
教育職員の精神疾患による病気休職者数は、7,119人(全教育職員数の0.77%)で、令和4年度(6,539人)から580人増加し、過去最多。最大の理由は「児童・生徒対応」であり、暴力・暴言による精神的負担が背景にあると推察される。
出典:文部科学省公式資料
文科省調査:教員への暴力行為の認知件数(2023年度)
全国の公立学校で、児童・生徒による教員への暴力行為が年間数千件単位で報告されている。文部科学省は「早期発見・毅然とした対応」を求めているが、事件化基準は曖昧。
出典:文部科学省 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
長野県中信地区の女性教諭が児童に暴言・体罰(2025年6月)
36歳の女性教諭が授業中に児童の頭や頬を複数回叩き、「くず」「死ね」「消えろ」などの暴言を繰り返した。児童側の挑発行為は報道されていないが、教員側のみが減給処分。
出典:TBS
千葉市教育委員会:校内死角の点検と暴力防止対策(2025年7月)
千葉市教育委員会は、校内の死角を点検する「校内死角改善確認シート」を導入。教員が児童から性暴力や暴力を受けるリスクを減らすための環境整備を進めている。
出典:読売新聞(2025年7月18日)
制度的空白と公務員倫理の崩壊
公立学校教員は地方公務員法第32条に基づき、法令遵守義務を負っている。児童から暴力を受けた場合、本来は通報や記録、適切な対応を取る義務がある。しかし、現場が「穏便に済ませる」ことを優先するあまり、通報をためらい、義務すら果たせない構造が生まれている。
文部科学省は「毅然とした対応」「早期発見・早期対応」「関係機関との連携」を基本方針としているが、児童から教員への暴力を刑事事件として扱うべきかについては明確な通達が存在しない。
出典:福島県教育委員会「暴力行為のない学校づくり」報告書
保護者の謝罪は教育的効果を持つか
子どもが家庭内で制御不能になっている状況では、親が謝っても現場の問題は何も解決しない。謝罪は儀式化し、教育的効果も抑止力も持たない。学校は「保護者が謝ったから一件落着」として処理するが、教員は「またか」と思いながら耐えるしかない。暴力の再発を防ぐには、謝罪ではなく、行動変容を促す制度的支援が必要である。
警察介入の教育的意義
暴力行為に対して制裁がなければ、子どもは「社会で許容されない行為が、学校では許される」と誤認する。家庭での指導が機能しない場合、警察や児童相談所など外部機関の介入は、教育的意味を持つ。これは罰ではなく、社会的責任を実感させるための措置である。
文部科学省は教員保護方針とともに、児童による暴力の事件化基準を明示すべきだ。教育現場の秩序を守るためには、学校内の暴力を「教育的に処理する」だけでは限界がある。
私立学校との制度的差異
私立学校であれば、暴力行為をした児童に対して退学処分を含む厳格な対応が可能であり、教員保護の裁量も広い。公立学校では、児童の処分に関して法的・制度的制約が多く、教育委員会の判断も保護者や地域の圧力に左右されやすい。結果として、教員が被害を受けても「穏便に済ませる」方針が優先される。
制度改革の必要性
公立学校教員が安心して働ける環境こそが、子どもたちの健全な成長を支える土台である。教育の信頼を回復するには、児童・保護者・教員・教育委員会・文部科学省の全員が責任を共有する姿勢が不可欠だ。教員保護方針の明文化、事件化基準の整備、外部機関との連携強化が急務である。