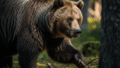現代日本では法律で禁じられている一夫多妻制。しかし、その概念は日本の歴史の中でどのように扱われてきたか。また、もし現代で似たような状況が起きた場合、法的にはどうなるか。
歴史に見る一夫多妻制の深掘り
上代(飛鳥・奈良時代)
この時代、天皇は複数の后を持つことが一般的だった。これは、皇位継承者を複数確保するためと、有力豪族との婚姻を通じて政治的な結びつきを強化する目的があった。例えば、天武天皇は皇后の他に複数の妃を持ち、その間の子どもたちが皇位継承権を争う基盤となった。貴族社会でも、妻問い婚という形態が主流だったため、男性が複数の女性の元に通うことは珍しくなかった。正妻とそれ以外の妻(めかけ)には明確な身分差が存在した。
中古(平安時代)
藤原氏の時代になると、摂関政治が展開され、娘を天皇の后として入内させ、その孫を天皇にすることで権力を握るのが常套手段となった。このため、天皇は複数の后妃を持ち、后の序列は彼女たちの父親の身分や権力によって決まった。貴族社会では、複数の女性と関係を持つことが男の甲斐性として認識され、一夫多妻多妾制がより洗練された形で続いた。
中世(鎌倉・室町時代)
武士の時代になると、家制度が確立し、家督を継ぐための嫡子をもうけることが重要視された。正妻以外の女性との間の子どもも、嫡子がいなければ家を継ぐことができた。しかし、戦乱が続いたため、庶民の間では一夫一妻が主流となり、複数の妻を養う余裕は少なかった。
近世(江戸時代)
幕藩体制下では、武士階級では正室と側室を持つことが一般的だった。これは、家名の存続と、有力な大名家との血縁関係を結ぶための政治的理由が大きかった。一方、庶民の間では一夫一婦制が原則だった。例外として、妻に子どもがいない場合や病気の場合などに限り、妾を持つことが黙認されることもあったが、経済的な負担から複数の女性を養うことは困難だった。
明治以降の天皇家
明治天皇は、明治以降に制定された皇室典範が定める一夫一妻制の適用外だった。明治天皇の時代は、皇后と複数の側室を持つことが認められていた。そのため、明治天皇の子どもは、皇后である昭憲皇太后との間に生まれた子どもはおらず、すべて側室との間の子どもである。
大正天皇以降は、皇室典範によって一夫一妻制が定められたため、正室と側室の区別はなく、天皇と皇后の間に生まれた子どもだけが皇位継承権を持つ。このため、大正天皇以降は、すべて天皇と皇后の子どもだ。
明治天皇 (122代)
- 皇后: 昭憲皇太后
- 子女: なし
- 側室:
- 権典侍 葉室光子(のち典侍)
- 権典侍 橋本夏子(のち典侍)
- 典侍 千種任子(のち権典侍)
- 典侍 柳原愛子
- 典侍 園祥子
- 子女(側室との間):
- 敬子内親王(千種任子との子)
- 梅宮薫子内親王(柳原愛子との子)
- 明宮嘉仁親王(後の大正天皇)(柳原愛子との子)
- 滋子内親王(園祥子との子)
- 増宮章子内親王(園祥子との子)
- 久宮静子内親王(園祥子との子)
- 昭宮猷仁親王(園祥子との子)
- 常宮昌子内親王(園祥子との子)
- 周宮房子内親王(園祥子との子)
- 富美宮允子内親王(園祥子との子)
- 泰宮聡子内親王(園祥子との子)
- 貞宮多喜子内親王(園祥子との子)
大正天皇 (123代)
- 皇后: 貞明皇后
- 子女:
- 迪宮裕仁親王(後の昭和天皇)
- 淳宮雍仁親王(秩父宮)
- 光宮宣仁親王(高松宮)
- 澄宮崇仁親王(三笠宮)
昭和天皇 (124代)
- 皇后: 香淳皇后
- 子女:
- 照宮成子内親王(盛厚王妃)
- 久宮祐子内親王
- 孝宮和子内親王(鷹司和子)
- 順宮厚子内親王(池田厚子)
- 継宮明仁親王(後の上皇)
- 清宮貴子内親王(島津貴子)
- 義宮正仁親王(常陸宮)
上皇 (125代)
- 皇后: 上皇后美智子
- 子女:
- 浩宮徳仁親王(今上天皇)
- 礼宮文仁親王(秋篠宮)
- 紀宮清子内親王(黒田清子)
今上天皇 (126代)
- 皇后: 皇后雅子
- 子女:
- 敬宮愛子内親王
現代日本と法律の壁
現代日本では、民法第732条で重婚が明確に禁止されている。これは、婚姻届を提出して法律上の夫婦になる場合に適用されるルールだ。そのため、一人の男性が複数の女性と正式に結婚することはできない。
事実婚と同居の場合
一人の男性が複数の女性と婚姻届を出さずに同居し、それぞれの子どもを育てている場合、それは法律違反ではない。なぜなら、法律上の婚姻関係がないからだ。この場合、それぞれの女性との関係は事実婚と見なされ、法的な不貞行為の概念も適用されない。
子どもの姓はどうなるか
この状況で生まれた子どもは、母親の戸籍に入り、母親の姓を名乗る。父親の姓を名乗らせたい場合は、父親が子どもを認知した上で、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる手続きが必要だ。
生活の維持は可能か
複数の女性と子どもを養うことは、法律上は問題ないが、多くの課題が伴う。経済的な負担や社会的な偏見、そして遺産相続などの法律上の複雑な問題が生じる可能性がある。