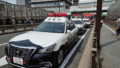御霊の「分離」を「分祀」と誤解
「靖国神社問題は、1978年のA級戦犯の合祀が原因である。この問題を解決するには、A級戦犯の分祀以外に方法はない」
古賀誠自民党元幹事長は、インタビューでこの見解を強調した。
しかし、A級戦犯被告人の御霊を靖国神社から取り除くことを「分祀」と発言しているが、「分祀」の意味を取り違えている。また、一度、合祀した御霊を取り除くことは、神道ではタブーであり、神道の神髄を破壊する行為である。
神道的観点から見た「分祀」と「合祀取消」の違い
| 用語 | 世俗的意味 | 神道的意味 | 教義上の可否 |
|---|---|---|---|
| 分祀 | 本社から分霊して別の神社に祀ること | 本来は尊厳ある拡張行為(例:分社) | 合祀された霊を別社に祀ることは可能だが、元社から除く意味ではない |
| 合祀取消 | 霊璽簿から霊を削除し、祭神としての地位を取り消すこと | 神道では極めて異例かつ困難な行為 | 教義上、原則不可(霊は一度祀れば永続) |
古賀誠氏の主な主張
- A級戦犯(実際はA級戦犯被告人)の合祀により、昭和天皇の親拝ができなくなった。
- 分祀が実現していない現状での首相や閣僚の靖国参拝には反対である。
- 東京裁判を否定する意見は、サンフランシスコ講和条約(正式名称は「日本国との平和条約」で、1951年9月8日にサンフランシスコで調印され、1952年4月28日に発効)で戦争責任を受諾した歴史認識と矛盾する。
- この問題が未解決なのは政治の貧困であり、われわれの世代で解決すべきである。
- 靖国問題が政治的に利用されることに危機感を持つ。
- 石破茂首相には、天皇陛下の親拝ができる環境整備の先頭に立つことを期待する。
靖国分祀、今の世代で解決を 古賀誠自民党元幹事長インタビュー(時事通信)
【魚拓】靖国分祀、今の世代で解決を 古賀誠自民党元幹事長インタビュー(時事通信) – Yahoo!ニュース(1ページ目)
【魚拓】靖国分祀、今の世代で解決を 古賀誠自民党元幹事長インタビュー(時事通信) – Yahoo!ニュース(2ページ目)
神道における「分祀」の本義
神道では「分祀」とは御霊を新たな神社に勧請することであり、既存の神社から「取り除く」ことではない。靖国神社や神社本庁は以下のような立場を取っている。
- 一度合祀された御霊は、神体に鎮められており、霊璽簿から名前を削除してもA級戦犯被告人合祀が無かったことにはならない。
- 分祀とは「分離」ではなく「分けて祀る」ことであり、元の神社の祭神は変わらない。
- 分祀の例えとして、「火は分けられても、元の火は消えない」という比喩が使われる。
このような神道の霊魂観に基づけば、古賀氏の「分祀すれば参拝問題は解決する」という主張は、神道の教義的理解と乖離している。
古賀氏は遺族会会長として、天皇陛下の靖国参拝を望みつつ、A級戦犯の分祀を主張しているが、以下のような矛盾が指摘されている。
矛盾点
| 観点 | 古賀氏の主張 | 神道的観点との矛盾 |
|---|---|---|
| 分祀の可能性 | 「分祀以外にない」 | 神道では分離は不可能 |
| 遺族の感情 | 「母の言葉が契機」 | 感情論が教義を凌駕している |
| 国際配慮 | 「近隣諸国への配慮」 | 神社の祭祀は外交とは無関係 |
| 政治的責任 | 「政治の貧困」 | 政治が宗教に介入する危険性 |
―靖国参拝時に母親が「赤紙を出した偉い人も一緒に入っている」とつぶやいたことが分祀論の契機になったのか。
https://news.yahoo.co.jp/articles/21d42d6e61c13d8ccc7b3781c507a3e3cfbe1453?page=1
犠牲者の妻として、命令を出した人と出されて死んだ人が、同じところに祭られていることに対する正直な気持ちだ。今でも母が言ったことは理解できるし、大切にしなくてはいけないと思っている。
―政治的にどう取り組むべきか。
この問題がいまだ解決できていないのは「政治の貧困」が続いているからだ。上皇さまが世界30カ所以上の慰霊の旅を続けられたが、靖国にお参りできていない。英霊もご親拝いただきたいのに、それができないのは残念だ。
構造的欠陥
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| 分離先の不在 | A級戦犯の御霊をどこに遷すのか、具体的な神社名や施設案は提示されていない。 |
| 神道的矛盾 | 神道では「分離」は成立せず、御霊は分けられても元の神座から除去できない。 |
| 宗教的手続きの不明瞭さ | 分祀には神職による正式な儀式が必要だが、その儀式の形式や神社間の合意も不明。 |
| 政治的配慮の優先 | 分離は外交的配慮や天皇のご親拝を可能にするための「政治的方便」として語られている。 |
古賀氏は、誰の味方なのか?という問いの構造
古賀氏は「全員の敵になりかねない」立場に自らを追い込んでいる。
| 視点 | 古賀氏の立場 | 問題点 |
|---|---|---|
| 遺族会会長 | 遺族の感情を代弁する立場 | しかし神社の教義や霊的秩序を無視している |
| 自民党元幹事長 | 保守政治の象徴的存在 | にもかかわらず、神道の伝統を破壊する提案 |
| 平和主義者 | 戦争責任の明確化を主張 | だが霊的秩序を政治的手段に変える危険性あり |
| 天皇参拝推進 | ご親拝の環境整備を目指す | 天皇は祭祀を司る最高神職であるのにもかかわらず、神道の本質を破壊(宗教的タブーを推進)する逆転構造 |
祟り(たたり)の事例
神道において、御霊を不適切に扱うことは「祟り(たたり)」を招くとされる。祟りとは、鎮められなかった霊が怒りや悲しみをもって現世に災いをもたらす現象であり、古代から現代に至るまで、神道儀礼の根底にある霊的倫理である。
御霊を「取り除く」ような暴挙は、霊的秩序の破壊であり、祟りの原因となる。
特に靖国神社のような国家的慰霊施設では、英霊の鎮魂が社会的安寧と結びついているため、その秩序を乱すことは国家的災厄を招く可能性すらある。
古賀氏の分祀論は、霊的秩序を軽視し、政治的都合で御霊を排除しようとするものであり、神道的には危険な発想である。
| 事例・背景 | 祟りの伝承・霊的含意 |
|---|---|
| 平将門の首塚(東京都千代田区) 朝廷に反旗を翻した将門は討伐され、首が京都から関東へ送られた。 | 首塚の移動や撤去を試みると、事故や病気が相次ぎ、死亡者も出た。 1940年の庁舎建設では工事が中止され、1980年代の再開発も地元の反対で断念。 将門は神田明神に祀られ、丁重に祀れば守護神、粗末に扱えば災厄をもたらすとされる。 |
| 菅原道真の怨霊(清涼殿落雷事件) 讒言(ざんげん)により太宰府に左遷され、失意のうちに死去。 | 道真の死後、清涼殿に落雷があり、関係者が次々に死去。 朝廷は恐れ、道真を神格化して天満宮に祀った。 怨霊を神として祀ることで祟りを鎮める「御霊信仰」の典型例。 |
| 崇徳天皇の怨霊(保元の乱) 乱に敗れ讃岐に流され、死後「日本第一の怨霊」とされた。 | 朝廷に災厄が続き、後白河法皇は祟りを恐れた。 明治期に白峯神宮が創建され、鎮魂の対象となった。 |
| 地霊・神木の祟り(全国各地) 聖域や禁忌地の破壊により祟りが起こるという伝承が各地に残る。 | 所沢市の「血の出る一本松」など、神木伐採による災厄の例がある。 古代の祭祀場や聖域の記憶が民間信仰として残ったと考えられる。 |