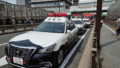高齢者婚姻と相続の交錯点
老人ホームでの高齢者婚姻をきっかけに、遺産相続をめぐるトラブルが多発している。認知症や判断能力が低下した高齢者が施設内で婚姻関係を結び、数千万円〜数億円規模の遺産が血縁外に流出する事例が報道されている。
これは家族間の感情的対立ではなく、民法・戸籍法・後見制度などの制度設計そのものが問われる構造的課題である。
報道事例
認知症男性の施設内再婚と数億円相続
認知症を患い施設に入所していた男性が、亡くなる半年前に高齢女性と婚姻。死後に戸籍を確認した家族が再婚の事実を知り、驚愕。遺産総額は数億円規模で、後妻が法定相続人として半分を取得する可能性が浮上。
「ノリ」で婚姻届が出された地面師的構造
施設スタッフや元夫が関与していた疑いもあり、「新手の後妻業」として司法書士が警鐘。家族が知らぬ間に婚姻届が提出され、女性側が遺産の半分を取得。
法定相続分の制度構造
民法上、婚姻関係にある配偶者は常に法定相続人となる。子がいても最低1/2の相続分を取得する。
| 相続人の構成 | 配偶者の法定相続分 | 子の法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子(1人) | 1/2 | 1/2 |
| 配偶者+子(2人) | 1/2 | 1/4ずつ |
| 配偶者のみ(子なし) | 全額(1/1) | – |
この構造が「婚姻による資産の半減」という感覚の制度的根拠となっている。
戸籍の不受理制度は有効か
婚姻届の「不受理申出制度」は、本人の意思によらない届出を役所が受理しない制度。認知症などで判断能力が低下した場合でも、事前に申出しておけば、勝手に婚姻届を出されるリスクを防げる。
ただし、本人が申出していない場合や、すでに婚姻届が受理された後では、婚姻無効確認訴訟などの法的手続きが必要になる。
高齢者婚姻による不当相続の防止策(法的手段)
| 手段 | 内容 | 有効性 | 留意点 |
|---|---|---|---|
| 不受理申出制度 | 本人の意思によらない婚姻届を拒否 | 高 | 事前申出が必要 |
| 成年後見制度 | 判断能力が低下した高齢者に後見人を付ける | 高 | 費用・手続きが重い |
| 家族信託 | 財産管理を家族に委託し、相続を制限 | 中 | 契約設計が複雑 |
| 公正証書遺言 | 死後の財産分配を明確化 | 中 | 婚姻後に変更される可能性あり |
| 婚姻無効確認訴訟 | 意思能力の欠如を裁判で争う | 低 | 証明が困難・時間がかかる |
| 遺留分侵害額請求 | 最低限の相続分を請求 | 中 | 後妻が全財産取得した場合に有効 |
| 婚姻禁止条項 | 施設契約に婚姻制限を設ける | 低 | 法的拘束力は弱い |
地面師と高齢者婚姻詐欺の構造的類似
| 項目 | 地面師詐欺 | 高齢者婚姻詐欺 |
|---|---|---|
| 標的 | 所有者不明の土地 | 判断能力が低下した高齢者 |
| 手口 | なりすまし・偽造書類 | 婚姻届の提出・相続権取得 |
| 被害 | 不動産売買詐欺 | 遺産の不当取得 |
| 防止策 | 登記制度・本人確認 | 戸籍制度・後見制度 |
地面師は他人の不動産の所有者になりすまし、偽造書類を使って不正に売却し、代金を騙し取る詐欺師。積水ハウス事件では約55億円の被害が発生した。高齢者婚姻詐欺は、これと構造的に酷似しており、制度の境界線を突く詐欺的構造といえる。
類型化される事例パターン
- 認知症・判断能力低下による婚姻
高齢男性が施設内で婚姻届を提出。家族が知らぬ間に婚姻が成立し、死後に後妻が法定相続人として遺産を取得。 - 隠し子・非嫡出子の登場
施設入居後に「腹違いの兄弟」や「隠し子」が現れ、遺産分割請求により家族が資産を手放す。 - 再婚による相続権の移動
高齢女性が再婚し、夫の死後に財産を取得。家族との関係が悪化し、絶縁・トラブルに発展。
制度設計的な論点整理
| 制度 | 問題点 | 改善余地 |
|---|---|---|
| 戸籍制度 | 本人確認が形式的 | 医師診断書の添付義務などの強化 |
| 婚姻制度 | 意思能力の確認がない | 高齢者婚姻における審査制度の導入 |
| 相続制度 | 血縁外への資産流出 | 遺留分制度の見直しと信託制度の普及 |
| 高齢者施設 | 倫理ガバナンスの欠如 | 第三者監査・婚姻届提出の通報義務化 |
さいごに
高齢者婚姻と相続の問題は、制度設計の脆弱性が露呈する社会的構造問題である。制度の境界線、意思能力の定義、財産の公共性などを問い直す視点が不可欠。制度の盲点を突く詐欺構造として、地面師と並列的に分析することで、制度設計の再構築に向けた議論が可能になる。