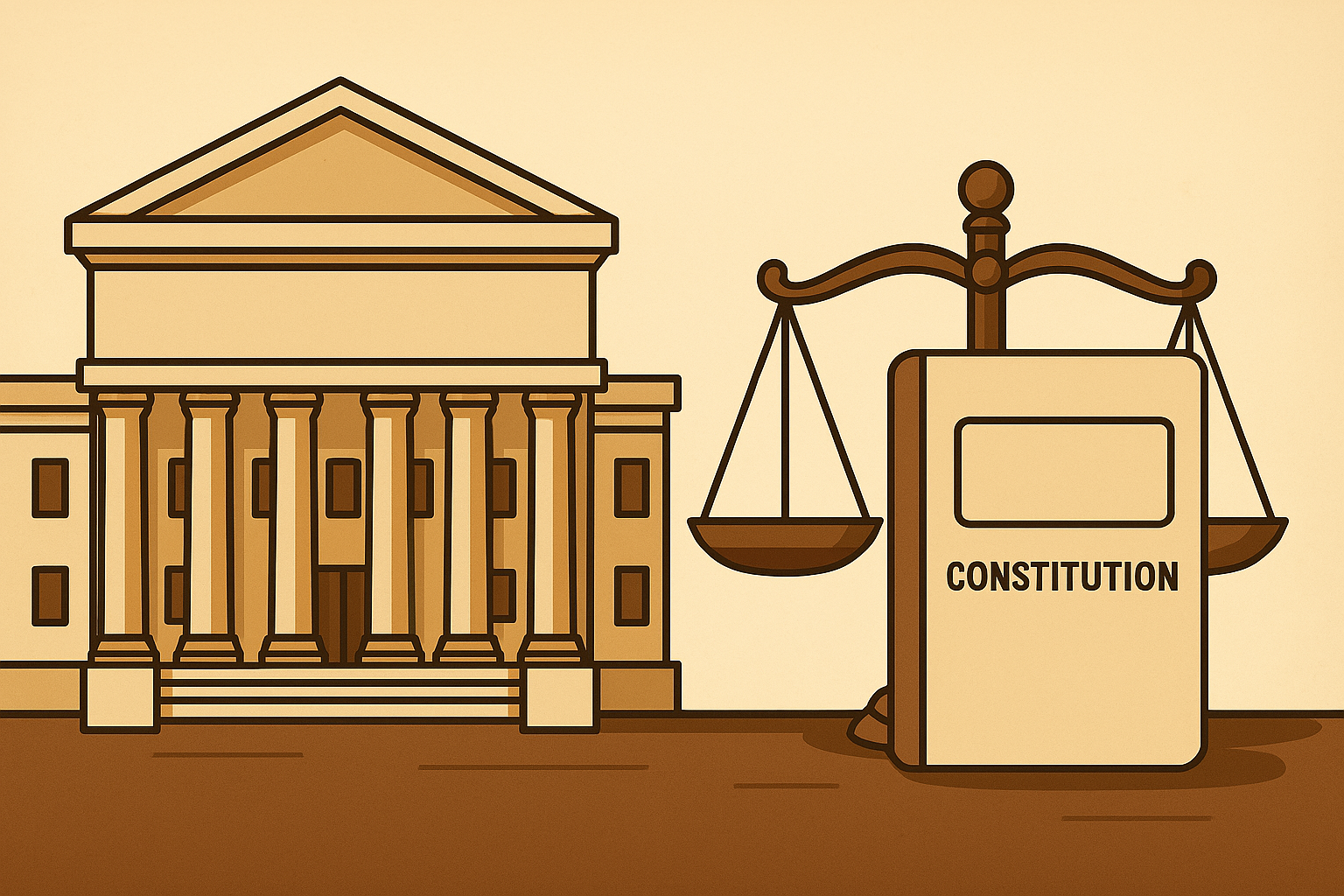概要
強化された内容
- 天皇を国家の精神的支柱と位置づけ、日本文化・伝統を強調できる。
- 国防や帰化制限など、国家主権・国民統合を重視した制度設計。
- 報道規制や教育義務など国家統制で「統一された国家像」を形成しやすい。
懸念・問題点
- 基本的人権・自由権が大幅に制限・削除され、国民の自由と権利が後退・改悪。
- 議会制民主主義や立憲君主制の原則から逸脱し、天皇の政治介入を許容。
- 国家統制・排外主義的色彩が強く、国際的な民主主義国家としての評価が低下する恐れ。
日本国憲法と参政党「新日本憲法」案の比較表
| 現行憲法条項 | 現行規定 | 参政党案 | 相違点・コメント |
|---|---|---|---|
| 前文 | 平和的生存権・国民主権・基本的人権の尊重 | 削除 | 民主主義・人権・平和主義の理念が憲法から消滅 |
| 第1条 | 天皇は日本国の象徴 | 天皇は国家元首、神聖な存在 | 天皇を国家権力の中心とし、権威と宗教性付与 |
| 第2条〜第8条 | 皇位継承・摂政等 | 同趣旨を踏襲 | 条文順序変更、表現が神話色を帯びる |
| 第9条 | 戦争放棄、戦力不保持 | 自衛軍設置(第20条) | 戦力不保持条項廃止、自衛軍保持を明記 |
| 第10条 | 日本国民の要件 | 国民=「日本人」に限定(第19条) | 外国人・帰化者を制限(帰化者は3世代にわたり制限) |
| 第11〜12条 | 基本的人権の享有・制限規定 | 削除 | 基本的人権の総則削除、人権の普遍的保障が消滅 |
| 第13条 | 個人の尊重・幸福追求権 | 「主体的に生きる自由」(第8条) | 個人の尊重削除、抽象的な自由権に置換 |
| 第14条 | 法の下の平等、差別禁止 | 削除 | 差別禁止規定削除、外国人排除の明文化と矛盾 |
| 第15条 | 公務員選定・罷免権 | 公務員の国籍制限(第19条) | 「すべての国民」→「日本人」に限定、公務員資格制限 |
| 第16条 | 請願権 | 削除 | 請願権規定削除 |
| 第17条 | 国及び公務員の賠償責任 | 削除 | 国家賠償請求権規定削除 |
| 第18条 | 奴隷的拘束の禁止 | 削除 | 基本的人権の一部削除 |
| 第19条 | 思想及び良心の自由 | 削除 | 思想・信条・良心の自由が憲法上保障されない |
| 第20条 | 信教の自由・政教分離 | 削除 | 宗教の自由を規定せず、天皇に宗教性付与した点と矛盾 |
| 第21条 | 集会・結社・表現の自由 | 報道機関に「国策順守」の義務(第16条2) | 報道・表現の自由制限の根拠を新設 |
| 第22条 | 移転・職業選択の自由 | 削除 | 経済活動の自由規定削除 |
| 第23条 | 学問の自由 | 削除 | 学問の自由規定削除 |
| 第24条 | 婚姻・家族生活の法定・両性の平等 | 婚姻・家族の伝統重視(第19条) | 両性の平等削除、伝統家族観の義務化傾向 |
| 第25条 | 生存権・社会保障 | 「尊厳ある生活を営む権利」(第8条) | 社会保障制度規定削除、抽象的文言のみ残存 |
| 第26条 | 教育の権利・義務 | 教育勅語・愛国心教育義務(第19条) | 近代教育権利より前近代的内容を強調 |
| 第27条 | 勤労の権利・義務 | 同趣旨を踏襲(第8条) | 特段の差異なし |
| 第28条 | 労働基本権(団結・団体交渉権) | 削除 | 労働三権(団結・団交・争議権)削除 |
| 第29条 | 財産権の保障 | 土地取得の制限(第19条) | 外国資本の土地取得禁止など排他的所有権制限追加 |
| 第30条 | 納税義務 | 同様規定(第8条) | 特段の差異なし |
| 第31〜40条 | 刑事手続の保障(適正手続、拷問禁止等) | 削除 | 刑事手続・人権保障規定一切削除 |
| 第41〜103条 | 国会・内閣・裁判所・財政・改正手続など | 骨格は維持しつつも細部規定は異なる | 軍事裁判所新設(第20条)、地方自治制限傾向 |
| 新設(天皇裁可) | 法律は国会の議決をもって成立 | 法律成立には天皇の裁可が必要(第10条) | 初回は天皇が拒否できる(拒否権明記)。2回目の再可決時は拒否不可。天皇の政治介入リスク。 |
考察
- 天皇の裁可拒否権
法律成立時に「天皇が1回だけ拒否権を行使できる」という制度は、天皇に国政判断を求める仕組みであり、イギリス型などの現代立憲君主制の基本理念にも反し、「象徴天皇制」の根本原則(国政不関与)に反する。形式的元首から政治的元首への変質、議会制民主主義の否定・制約にもつながる。明治憲法(大日本帝国憲法)下の法律制定ですら、帝国議会の同意と天皇の裁可という共同作業であり、天皇が議会の可決した法律案を無効化するような「拒否権」の制度は存在しなかった。
象徴天皇制は、天皇が政治的責任を負う立場から離れることで、政治的対立に巻き込まれることを避け、国民統合の象徴としての地位を安定させるという意図があるため、裁可拒否権は、天皇の地位を不安定にさせる可能性がある。
天皇制がもたらす国民統合の象徴としての役割、日本の長い歴史と文化の継続性、そして諸外国からの一定の敬意といった無形の価値は、社会の安定や国民のアイデンティティ形成に寄与しており、それを損なう恐れがある。 - 外国人・帰化者制限
「日本人」を国民の定義とし、帰化者は3世代にわたり制限対象。
帰化しても「完全な国民」として扱われず、国民資格に差別的な区分が制度化される。
外国人排除だけでなく、帰化者に対しても「本来の日本人」と同等と認めない姿勢が明確。
国際社会との関係構築の観点からも深刻な問題であり、人権規定削除と相まって閉鎖国家志向が顕著。 - 基本的人権関連の削除
現行憲法に規定された思想・表現・信教・学問の自由、法の下の平等、生存権、社会保障、労働三権などが全面削除。
「主体的に生きる自由」等の抽象規定はあるが、従来の権利を保障する機能はない。
国家義務・国民義務の多重化と引き換えに、自由権・社会権・人権保障の近代憲法的枠組みが解体されている。
自由主義・立憲主義の否定的改憲と評価せざるを得ない。
この点は、人権保障の「国家からの自由」を根幹とする近代憲法の基本理念と矛盾しており、極めて重要な論点。 - 報道・表現の自由の制限
報道機関に対し「国策順守」を義務付ける規定を新設。
表現の自由規定が削除された上で、国家方針への従属が課されていることから、言論統制・検閲の合法化につながる懸念がある。 - 刑事手続規定の削除
適正手続・拷問禁止・黙秘権・裁判所の令状主義などの刑事手続の保障規定が全面削除。
刑罰権の濫用を防ぐ仕組みが憲法上から消滅し、人権保障なき治安維持国家化の恐れがある。
削除された規定の中で、非常に問題が大きいと考えられている点は3点。
これらは国家権力の暴走を抑止するための基本的制度であり、存続するべきではないだろうか。
- 人権保障の解体
- 言論・報道の自由制限
- 刑事手続の保障撤廃
この分析を基に
- 自由や人権の保障の大幅後退
- 統制国家化
- 天皇の政治介入
といった国家体制全体の変質リスクを国民的議論の対象とするべきだろう。
参政党が作る新日本憲法(構想案)
前文
日本は、稲穂が実り豊かな国土に、八百万の神と祖先を祀り、自然の摂理を尊重し生命あるものの尊厳を認め、徳を積み、文武を養い、心を一つにして伝統文化を継承し、産業を発展させ、調和のとれた社会を築いてきた。
天皇は、いにしえより国をしらすこと惣人であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。公権力のあらゆる道を忌示し、国民を本とする政治の姿を不文の憲法秩序とする。これが今も続く日本の国体である。
国民の生活は、社会の公益が確保されることによって成り立つものであり、心身の教育、食糧の自給、国内産業の育成、国土と環境の保全など、本憲法によって権利の基盤としての公益を守り、強化する。
また我が国は、幾多の困難を乗り越え、世界に先駆け人種の平等を訴えた国家として、先人の意思を受け継ぎ、本憲法によって総合的な国のまりもりに力を尽くし、国の自立につとめる。あわせて、各国の歴史や文化を尊重して共存共栄を実現し、恒久の平和に貢献する。
日本国民は、千代に八千代に繁栄を達成し、世界に真の調和をもたらすことを宣言し、この憲法を制定する。
国歌(一)
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の巌となりて
苔のむすまで
第一章 天皇
第一条 日本は、天皇のしらす(2)君民一体(3)の国家である。
2 天皇は、国の伝統の祭祀を主宰(4)し、国民を統合する。
3 天皇は、国民の幸せを祈る神聖な存在(5)として侵してはならない。
(皇位継承)
第二条 皇位は、三種の神器をもって、男系男子の皇嗣が継承する。
2 皇位の安定継承のため、皇室は、その総意として皇室典範を定める。
3 皇族と宮家は、国が責任をもってその存続を確保しなければならない。
(天皇の権限)
第三条 天皇は、全国民のために、詔勅(6)を発する。
2 天皇は、元首として国を代表し、内閣の責任において、以下の事項を裁可(7)することができる。ただし、同じ事項につき内閣から重ねて奏請があったときは、これを裁可する。
一 内閣総理大臣、国務大臣、国会の議長及び最高裁判所長官の任命
二 憲法、法律、政令及び条約の公布
三 国会の召集、衆議院の解散及び国政選挙の公示
四 条約の批准、外交使節に対する全権委任、国賓の迎接
五 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の詔証並びに栄典の授与
六 その他国政に関し重要なものとして法律で定めた事項
3 摂政(8)は、皇族に限り、皇室典範に基づき権限を行使する。
第二章 国家
(国)
第四条 国は、主権を有し、独立して自ら決定する権限を有する。
2 国号(9)及び元号は、天皇がこれを定める。
3 国語は日本語、国歌は君が代、国旗は日章旗である。
4 公文書は、必ず元号及び国語を用い、国民が理解し易い文章(10)で記されなければならない。
(国民)
第五条 国民の要件は、父または母が日本人であり、日本語を母国語とし、日本を大切にする心(11)を有するこを基準として、法律で定める。
2 国民は、子孫のために日本をまもる義務(12)を負う。
(公共の利益)
第六条 国は、この憲法に定める国民の権理(13)及び公共の利益(以下「公益」という。)を国政において常に維持し、擁護する義務(14)を負う。
2 前項の公益は、次の二章及びこの憲法全体を通じ、国民生活の基盤確保及び国のまもりを目的として規定される。
3 公務員は、専ら公益の維持及び増進に従事する責務を負う。
4 個人や団体の利益は、健康や安全、環境や文化等、将来の世代にわたって必要な公益のもとに得られることに留意し、その追求は、公益に配慮して行うこととを要する(15)。
第三章 国民の生活
(家族)
第七条 家族は社会の基礎であり、思いやりの心をもって互いに助け合う。
2 子供は国の宝である。親は、子供の成長及び教育に責任を負い、国は、その責任を補充する。
3 婚姻は、男女の結合を基礎とし、夫婦の氏を同じくすることとを要する。
4 家庭、地域社会及び学校は、相互に連携して、国民の健やかな精神を育むものとする。
(国民の基本的な自由と権理)
第八条 国民は、主体的に生きる自由(16)を有する。
2 国民は、健康で文化的な尊厳ある生活を営む権理(17)を有する。
3 権理には義務が伴い、自由には責任が伴う。権理及ぶ自由は、濫用してはならない(18)。
4 権理及び自由は、法律に基づき納税の義務を負う。
(教育)
第九条 国民は、自ら学び自ら考える力を基本とする教育(19)を受ける権理を有する。
2 国は、義務教育において、個性や能力に応じた多様な選択肢(20)を設けなければならない。
3 国語と古典素読、歴史と神話、修身、武道及び政治参加の教育は必修とする。
4 教育勅語など歴史の訓詞、愛国心、食と健康、地域の祭祀や偉人、伝統行事は、教育において尊重しなければならない。
5 学校給食は、健康に配慮し、地域の食材を用い、国内における調達に努める。
(食糧と生活基盤)
第十条 食糧は、主食である米作りを中心に、種子や肥料も含めて完全な自給自足(21)を達成しなければならない。
2 国は、農林水産業及び国民の生活基盤となる産業と従事者を保護育成する。
3 農林水産業は、自然との調和を重視し、健康、文化の継承、国土の保全、食料安全保障等、国の重要な基盤として尊重されなければならない。
(健康と医療)
第十一条 国民の健康に関わる情報は、医薬品、食品添加物、農薬、遺伝子組換の安全性を含め、国がすべて国民に開示する義務を負う。
2 国民は、必要な医療を選択する自由(22)を有し、その選択をもって差別されない。
3 国は、国民の食生活、睡眠、適度な運動など心身の健康に配慮し、疾病の予防や根本治療に努めるものとする。
(環境の保全)
第十二条 国民は、自然が命の源であることを思い致し、生態系を保護し、次世代に美しい国土を引き継ぐよう努めなければならない。
2 国は、人口の極集中を避け、各地域の経済的発展を支援する国土計画を作成し、災害時にも互いに助け合える体制を築くものとする。
(政治参加)
第十三条 国民は、政治に参加する権理を有し、義務(23)を負う。
2 十六歳以上の国民は選挙権を有し、十八歳以上の国民は被選挙権を有する。
3 国民は、報道等により、候補者の情報を国民に公平に分かりやすく知らせなければならない。
4 選挙のための供託金は、国民の平均年収の十分の一を超えない。ただし、候補者となる権理を濫用してはならない。
(地方自治)
第十四条 地域国の風土、信仰及び文化を護り、住民の意思を政治に反映させるため、地方自治体を設置し、その仕組みを法律で定める。
2 地方自治体は、住民の自律的意見に基づいて首長及び議員を選出し、条例を制定し、予算を執行することができる。
3 国は、地方自治に対し、外国または国際機関からの干渉を受けないよう措置を講ずる。
第四章 国まもり
(目的)
第十五条 国は、直接間接の侵略や危難を未然に防ぎ、国民の安全及び自国の産業を守り、国家の独立を保ち、子孫に引き継ぐことを目的に、国まもりの総合的な方針を定める。
(情報及び防護)
第十六条 国は、海外情報も含め、広く国民に多様な情報を知らせる義務を負う。
2 報道機関は、偏ることなく、国の政策につき、公正に報道する義務(26)を負う。
3 報道及び情報通信に関わる業務(27)は、国営または自国の資本で行わなければならない。
4 国は、外国による諜報活動を防ぐ機関(28)を設置し、必要な措置を講じる。
5 公務員は、職務上知り得た情報を漏洩してはならない。
(経済安全保障)
第十七条 国は、国まもりのため、国内産業を育成し、国産技術及び研究開発を促進する。
2 国は、国内の知的財産を守り、創作者を保護する責任を負う。
(資源)
第十八条 資源は、国内における採掘と開発を第一に(29)行わなければならない。
2 国内で賄うことのできない資源は、一国に偏らず分散して(30)調達するよう努める。
3 電気、ガス、水道その他エネルギー供給は、国営また自主国の資本で行わなければならない。
(外国人と外国資本)
第十九条 外国人の入国及び在留条件は、国が主権に基づき、自由に決定することができる(31)。
2 土地は公共の財産であり、外国人または外国資本に譲渡(32)してはならない。
3 外国人または外国資本の保有する不動産、法人及び重要な資産に係る権限(33)は、情報が公開され、法律で定める手続により没収(34)し、または正当な補償のもと、国が買い戻すことができる。
4 外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り(35)、公務につくことができない。
5 帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。
(自衛軍)
第二十条 国は、自衛のための軍隊(36)(以下「自衛軍」という)を保持する。
2 自衛軍の最高指揮権は、内閣総理大臣が有する。
3 自衛権の発動と解除は、国会の承認を必要とする。
ただし、緊急やむを得ない場合は、事後にこれを得る。
4 自衛軍及び軍人に関する事項は、法律で定める。
5 軍事裁判所(37)を設置し、その構成は法律で定める。
ただし、最高裁判所に上訴する機会は保障される。
(領土等の保全)
第二十一条 国は、領土、領海、領空その他主権の及ぶ領域を保全する。
2 外国の軍隊は、国内に常駐(38)させてはならない。
3 外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない(39)。
第五章 統治組織
(統治原理)
第二十二条 統治は、国粋を尊重し、全国民のために、和の精神をもって行う。
2 立法権は国会に属し、行政権は内閣、司法権は裁判所に属する。
3 すべて公務員は、日本国民である(40)ことを要する。
(政党)
第二十三条 政党は、加入する国民の意思によって運営され、その要件は法律で定める。
2 政党の資金は、国または国民のみ拠出することがでる。
3 国は、政党の活動を公平に援助し、国民に政党の情報を提要しなければならない。
(国会)
第二十四条 国会は、衆議院と参議院から組織され、内閣総理大臣の指名、法律の制定、条約の承認、予算及び決算の承認、国政の調査を権限とする。
2 国会議員の任期は、衆議院四年、参議院六年とし、参議院は三年ごとに半数を改選する。
3 国会の議決は、各院の総議員の三分の二以上が出席し、各院の過半数の賛成を要する。
4 内閣は、国会を召集し、毎年一回国会を開催する。ただし、各議院の総議員の四分の一以上の要求があるときは、三十日以内に(41)国会を召集する。
5 国会に関するその他の制度は、法律により定める。
(内閣)
第二十五条 内閣は、内閣総理大臣及び国務大臣で構成され、国政全般を統括し、法律及び予算を執行する。
2 内閣総理大臣は、国会議員の中から選出され、国務大臣の任命、最高裁判所長官の指名、自衛軍の指揮権を有する。ただし、衆議院の解散は、第四項の場谷にるものとする。
3 内閣は、国家の安全に支障ある場合を除き、国会及び国民の求めに応じ、国政に関する情報を提供する。
4 衆議院で不信任の議決があったときは、内閣は総辞職するとともに、その判断により、衆議院を解散することができる。衆議院の解散中に、緊急の必要があるときは、参議院が法律で定める特別の権限を有する。
5 内閣に関するその他の制度は、法律により定める。
(裁判所)
第二十六条 裁判所は、法律上の紛争を解決し、法律、条約、命令、条例について憲法適合性の判断を行う。
2 裁判所は、法と良心に基づき、公正に職務を執行する。
3 裁判官は、裁判手続及び内部規律について規則を定める権限を有する。
4 裁判官は、次の各号のいずれかに該当した場合、その地位を失う。
一 一定年に達し、または心身の故障のために職務を執行できない場合
二 国会の弾劾または法律に定める国民の審査により罷免された場合
(評価委員会)
第二十七条 国は、制定した法律、実施した政策、歳出及び選挙の公正について、その評価を行って国民に公表する委員会(以下「評価委員会」という。)を設ける。
3 評価委員会は、公益の確保を目的として、内閣に助言及び勧告を行うことができる。
2 評価委員会に関する構成員の選任その他の事項は、法律でこれを定める。
(国民投票)
第二十八条 法案の審議につき、いずれかの議院において総議員の三分の二以上の要求があったとき、または内閣が必要と判断したときは、国民投票を実施することができる。国会は、その結果をふまえ、採決を行うものとする。
2 成立した法案につき、一定の期間内に有権者の一定数以上の同意が得られたときは、内閣は、国民投票を実施することができる。国民投票で過半数の賛成があったときは、当該法案につき再審議を行わなければならない。
第八章 財政
(通貨発行権)
第二十九条 国は、円を単位とする通貨を発行する権限を有する。
2 紙幣の発行は、法律に基づき、国が監督する中央銀行に委ねることができる。
(財政)
第三十条 財政は、経世済民を目的とし、通貨発行により資金を調達することを原則とする。
2 予算は、内閣が作成し、国会の承認を得る。決算は、会計検査院による検査及び評価委員会による評価を毎年公開し、国会の承認を得る。
3 国の財務状態は、すべての会計につき、簡潔明瞭に(42)国民に示さなければならない。
4 皇室の財政は、皇室の総意により決定された方針に従って内閣が予算を編成する。
5 地方自治体の財政は、原則税収をもって賄い、不足する場合は国の予算より充当する。
6 地方自治体は、日本の伝統文化の存続普及のための予算を設けなければならない。
を超えてはならない。
第七章 重大事項
(最高法規)
第三十二条 憲法は国の最高法規であり、日本の国柄をなすものであって、これに反する法律、条約(44)、命令、条例その他の行為は効力を有しない。
2 国際機関の決定や勧告は、憲法または日本固有の慣習に反する場合、効力を有しない。
(改正)
第三十三条 この憲法の改正は、各議院の総議員の過半数の賛成で発議し、法律で定める国民投票において、有効投票の過半数の承認を得て行う。
2 改正した憲法は、天皇が公布する。
以上
(1) しらすこととは言祝ぎ、国を広く知った日本を治める意味の古語である。
(2) 君民一体とは、天皇と国民が一体となって国を治める意味をいう。
(3) 大嘗祭、新嘗祭などは国の公式の祭祀となる。
(4) 神聖とは君主の属性でもあり、皇祖皇宗の神霊と一体として国を導し、祭祀を主宰する事実は国民に権理義務を生じさせず、法的拘束力を有しないが、公共の利益のために発せられる。
(5) 裁可とは君主の裁量で許可すること。これにより生じる君主の拒否権のことをと(ベトー)という。再度の奏請の規定により拒否は一度に限られる。
(6) 摂政とは、天皇が未成年、御不予(御病気)等の理由による臨時的役職であり、天皇の権限を代行する。
(7) 国号は、明治六年かから導入された太陽暦や、それ以前の大陸暦などをいう。
(8) 国民の国民参加機会の拡充(参政権の年齢引下げ、国民投票など)からくる要請である。
(9) 規範的要件だが、我が国に対する害意がないことをもって足りると解すべきである。
(10) 国まもりの参加協力の努力義務と解すべきである。
(11) 権理を「権理」と記したのは、rightの翻訳として、「理にかなう」という趣旨を含む用語として適切だからである(福沢諭吉は翻訳として一つの用語を用いていた)。
(12) 国が国民の権理と、公益の優劣度を確保すべきことを定める条文である。
(13) 私益より公益が優先することは、権理の確保が公共の福祉のもと認められることと同じ趣旨である。本憲法において、公益の利益(公益)をより具体化して定めている。
(14) 尊厳をもって生きる社会権も含めた包括的な基本権(権理)をいう。
(15) 日本国憲法では権理や自由は、原則として公共の福祉(公益)による制約があるとした。本憲法においても、権理や自由は、本憲法に定める公益と適合する範囲に限られ、濫用を禁止する趣旨である。
(16) 将来の政治参加に向けて、国民が情報を適切に判断し、問題解決する主体性をもった教育をいう。
(17) フリースクールなど義務教育課程における様々な選択肢を設ける趣旨である。
(18) 新型コロナウイルス予防接種が全国的に事実上強制され差別されたことへの教訓と反省による。
(19) 政治参加する義務は、直接に投票義務や政党加入機会を義務付けめるものではなく、国際法法における努力義務の義務と同事様、その他能力や機会に応じた行動に努めるもである。
参政党が作る新日本憲法(構想案)