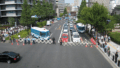戦争責任の問いを再構築する
戦争責任とは、誰が罰せられるかという「制度の問題」であると同時に、誰が記憶を引き受け、象徴として残るかという「社会の記憶と意味づけの問題」でもある。
とりわけ昭和天皇の戦争責任は、東京裁判の枠組みを超えて、倫理的・思想的な問いとして今なお私たちの前に立ち現れる。
1945年9月27日に行われた昭和天皇とマッカーサーの会見を起点に、「責任とは何か」「象徴とは何か」「記憶は誰に託されるのか」という問いを掘り下げていく。
制度的責任と実質的責任の交錯
制度的責任の所在
- 大日本帝国憲法下、天皇は「統治権の総攬者」として軍の最高指揮権を有していた。
- 宣戦布告・講和条約は天皇の名において行われたが、実際の政策決定は軍部・内閣によって主導された。
第四條
大日本帝国憲法
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
昭和天皇の政治的判断と御前会議発言の統合年表
| 年代 | 出来事・議題 | 昭和天皇の判断・発言 | 発言形式・態度 | 出典・備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1931年 | 満州事変 | 軍部の暴走に懸念を示すが黙認 | 事後報告に沈黙 | 『昭和天皇実録』 |
| 1936年 | 二・二六事件 | 「反乱軍鎮圧」を強く命令 | 明確な命令 | 陸軍首脳に「断固鎮圧せよ」 |
| 1940年 | 日独伊三国同盟(御前会議) | 消極的だったが最終的に承認 | 明確な反対なし | 松岡洋右の強硬姿勢に押される |
| 1941年9月6日 | 対米戦準備(帝国国策遂行要領) | 明治天皇の御製を詠む:「よもの海…」 | 和歌による象徴的反対 | 御前会議での発言記録 |
| 1941年12月1日 | 対米英蘭開戦決定(御前会議) | 「戦争は嫌だ」と発言するも容認 | 消極的容認 | 皇統維持を優先 |
| 1945年8月10日 | ポツダム宣言受諾(第一次聖断) | 「国民の苦しみを終わらせたい」 | 明確な和平決断 | 御前会議で軍部を退ける |
| 1945年8月14日 | ポツダム宣言受諾(第二次聖断) | 「日本を維持するには戦争を終わらせるしかない」 | 再度の聖断 | 終戦の詔書:「耐え難きを耐え…」 |
| 1945年9月27日 | マッカーサーとの会見 | 「すべての責任は私にある」 | 個人的責任の表明 | 占領政策に影響 |
| 1946年 | 退位論への対応 | 「退位するつもりはない」と側近に明言 | 皇統維持を最優先 | 昭和天皇の側近記録より |
分析の視点
- 沈黙から発言へ:1930年代は軍部の既成事実に沈黙で応じる場面が多かったが、1945年には明確な「聖断」によって政治的方向を決定。
- 象徴的表現から直接的言語へ:和歌による婉曲な反対(1941年)から、国民の苦しみや責任を語る直接的表現(1945年)へと変化。
- 皇統維持の一貫性:戦争容認も終戦決断も、根底には「皇統の存続」が判断基準として貫かれている。
昭和天皇の発言 – 倫理的責任の引受
歴史的発言(マッカーサー回顧録より)
「私は、戦争を遂行するにあたって日本国民が政治、軍事両面で行なったすべての決定と行動に対して、責任を負うべき唯一人の者です。あなたが代表する連合国の裁定に、私自身を委ねるためにここに来ました」
この言葉は、制度的責任を超えて「人格的責任」を引き受ける姿勢を示している。敗戦という断絶のなかで、天皇は自己保身ではなく国民の安寧を願って行動した。
昭和天皇の戦争責任は、東京裁判の枠組みを超えて、倫理的・思想的な問いとして今なお私たちの前に立ち現れる。
国民への配慮
「罪なき八千万の国民が、住むに家なく、着るに衣なく、食べるに食なき姿において、深憂に耐えません」
この発言は、象徴としての天皇が「国民の苦しみを引き受ける存在」であることを示している。
マッカーサーの反応 – 人格への敬意と制度設計の転換
回顧録の記述
「私は、すぐ前にいる天皇が、一人の人間としても日本で最高の紳士であると思った」
この感動は、占領政策の根幹を揺るがすものであった。マッカーサーは天皇を訴追せず、日本の占領統治を円滑に進める上で、天皇の存在が不可欠だと判断した。
占領政策への影響
1. 占領政策への影響:天皇制の存続と政治的配慮
1945年の敗戦後、日本は連合国の占領下に置かれ、GHQ(連合国軍総司令部)による抜本的な制度改革が進められた。とくに注目されたのが「天皇制の存廃」である。
- GHQ内部では、天皇の戦争責任を問うべきか否かで意見が分かれていた。
- 一部の米国メディアや連合国関係者は「天皇訴追」を主張したが、マッカーサーはこれを退けた。
- 1945年9月27日、昭和天皇とマッカーサーの会見において、天皇は「すべての責任は私にある」と発言。これがマッカーサーの心証を大きく変えたとされる。
この会見は、天皇制の存続を占領政策の安定装置として位置づける転機となった。
2. 天皇訴追の回避:政治的妥協と象徴化への布石
天皇の戦争責任を問う声は国内外に存在したが、最終的に訴追は回避された。その背景には複数の要因がある。
- 日本国内の混乱を避けるため、天皇制の急激な廃止は危険視された。
- マッカーサーは「天皇を訴追すれば100万人の占領軍が必要になる」と述べたとされる。
- 昭和天皇自身も、退位論に対して「退位するつもりはない」と側近に明言し、皇統維持の意志を貫いた。
この訴追回避は、天皇制の「制度的再定義」への道を開いた。
3. 象徴天皇制の確立:憲法と制度の再構築
1946年、日本国憲法の起草が進む中で、天皇の地位は大きく変容する。
- 新憲法第1章において、天皇は「日本国および日本国民統合の象徴」と規定された。
- 統治権の総攬者から、儀礼的・象徴的存在へと制度的に転換。
- 昭和天皇はこの変化を受け入れ、政治的発言を控える姿勢を強めた。
この象徴天皇制は、戦後日本の民主化と国民統合の象徴装置として機能した。
4. 全国巡幸による国民との再接続:象徴の実践
制度上の象徴化だけでなく、昭和天皇は「象徴としての実践」にも踏み出した。
- 1946年から1954年にかけて、全国巡幸を実施。被災地や農村を訪問し、国民と直接対話。
- 巡幸は「慰問」だけでなく、「再接続」の儀礼として機能。天皇の存在を再び国民の生活空間に位置づけた。
- 多くの国民が「涙ながらに拝謁した」と記録されており、象徴天皇制の感情的基盤を形成した。
この巡幸は、制度的象徴を「身体的・空間的象徴」へと拡張する試みだった。
戦争責任とは「記憶の倫理」である
昭和天皇の行動は、戦争責任を制度的処罰ではなく「人格的記憶の引受」として体現した。それは、靖国や慰霊碑とは異なる「沈黙と象徴」の記憶のかたちであり、戦後日本の制度と思想の交錯点に位置する。
戦争責任とは、誰が裁かれるかではなく、誰が記憶を引き受けるかという問いである。そしてその問いは、今もなお、私たちの公共空間に沈黙のかたちで息づいている。