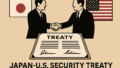投票箱・鍵管理・開票機械化と透明性の真実
日本の公職選挙は、「不正の入り込む余地がない仕組み」として国際的にも高く評価されている。その裏には地味で徹底した不正防止策がある。今回は、投票箱管理・鍵管理・輸送・開票所での不正防止、さらに開票機械の実態まで含めて、その仕組みを解説する。
投票箱の不正防止策
投票開始前:「空箱確認」
投票開始前には、立会人(市民から選ばれる)立会いのもと
- 投票箱の中身が空であることを確認し
- その場で施錠する。
この工程は公職選挙法に基づく正式手順。
投票中:施錠と監視
- 投票箱は常に施錠状態。
- ふたは狭い投入口しかなく、投票用紙以外は入れられない構造。
- 立会人と選挙管理委員会職員が常時監視している。
(投票管理者)
第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができる。
5 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
7 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する選挙人がした第四十九条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
(投票立会人)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
投票終了後:再施錠と鍵管理
- 投票終了後は南京錠などで再施錠。
- 必要に応じて封印シールなどを併用し、開封すれば一目で分かる状態に。
- 鍵は選挙管理委員会の管理責任者が保管し、本体と鍵は別々の職員が管理。
(投票箱の閉鎖)
第五十三条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
輸送時
投票箱輸送は、不正リスクが最も高まる工程。これを防ぐため次の対策が取られる。
- 施錠・封印したまま輸送。箱自体は物理的に開けられない状態。
- 南京錠の鍵は箱と別管理。同じ輸送車に鍵と箱を載せることは避けるのが原則。
- 選管職員または立会人が同行し、輸送中も監視。
- 封印番号を控え、到着時に番号を照合して箱のすり替えを防止。
- 輸送中は途中停車を最小限にし、原則開票所へ直行。
- 輸送記録(日時・車両・責任者名)を残し、証拠とする。
輸送には自治体職員の公用車が使われることもあれば、都市部では業者委託されることもあるが、その場合も職員が同行し監視する。
(投票箱等の送致)
第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。
開票時の不正防止策
公開原則
- 開票作業はすべて公開されている。
- 開票所に誰でも見学に入ることができ、作業全体が外部から監視可能。
人手作業の理由
- 票の分類・集計は人間の目視と手作業が基本。
- 機械に任せず、人の目と手で開票作業を進めるのは、「機械内部で不正操作される」リスクを排除するため。
票の束と集計
- 票は一定数ごとに束ねられ、束単位で数量が確認される。
- 一人の職員が票束を単独で扱うことは許されず、必ず複数人の監視下で作業。
- 不正疑惑が出れば、その場で再点検可能。
作業員の服装まで規定
- 開票作業員はポケットのないエプロンを着用させられることもある。
- 「票を持ち出す」「隠す」といった不正を物理的に不可能にするため。
機械は使われているのか?
実際には、票の分類や仕分けに専用機械が使われている。
自書式投票用紙読取分類機 テラックCRS-VAn
- 手書きの漢字・ひらがな・カタカナを毎分660票で読み取り分類。
- 最大125段の分類棚で、大規模選挙にも対応。
- 投票用紙の天地表裏を揃える反転ユニットも備える。
- スタッカーが満杯になっても処理を止めず分類を継続できる。
では機械で不正が行えるのか?
- テラックCRS-VAnは票を分類するだけの機械。
- 機械内部で票の書き換えや抜き取りが行える構造ではない。
- 仕分け後の票束は必ず人間が目視確認し、集計結果は開票管理者と立会人が確定する。
日本流:「機械+人間」の二重チェック
- 機械で効率よく分類し、
- 人間が確認して集計する。
これが日本の選挙の特徴。完全機械化せず、「人の目」を排除しないのが最大の不正防止策と言える。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第六十七条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第六十八条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
結論:アナログと機械の融合で「不正を物理的に排除」
- 投票箱と鍵の厳重管理。
- 開票作業は公開、かつ手作業中心。
- 機械は仕分けまで、集計は人間。
- 「誰でも目で見て確認できる仕組み」によって、日本の選挙は不正防止されている。
不透明な電子投票とは違い、日本の選挙は見える仕組みで守られている。この「地味な仕組みの積み重ね」が、選挙の公正さを支えている。